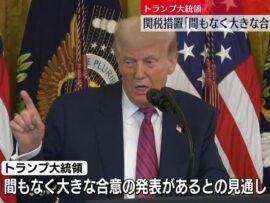日本の裁判官と聞くと、多くの人は公正中立で、高い知性と倫理観を持った人物像を思い浮かべるでしょう。しかし、現実は必ずしもそうではありません。元裁判官で法学者の瀬木比呂志氏の名著『絶望の裁判所』(講談社現代新書)では、日本の裁判所の知られざる実態が赤裸々に描かれています。本記事では、同書を基に、裁判官の知的怠慢という問題点に焦点を当て、その実態を分かりやすく解説します。
知的怠慢が蔓延する裁判所
 法廷のイメージ
法廷のイメージ
瀬木氏によると、現代の裁判官には深い教養や広い視野を持つ人が少ないといいます。専門外の読書をほとんどしない人も多く、心理学や精神分析、カウンセリングといった裁判官として知っておくべき知識さえ欠いているケースも珍しくないようです。
一般教養の不足は、多角的な視点や将来を見据えたビジョンを持つことを阻害します。そして、法律の知識さえあれば良いという驕りが、知的怠慢につながっていると言えるでしょう。瀬木氏は、こうした知的怠慢が裁判所内に蔓延していると警鐘を鳴らしています。
事件処理を優先する風潮
 裁判官のイメージ
裁判官のイメージ
裁判官の多くは、事件を迅速かつ円滑に「処理」することに重点を置いています。市民の些細な争いには無関心で、冤罪の可能性にも目を向けず、淡々と処理することに終始する傾向があるようです。
権力者や政治家、大企業などの意向に沿って秩序を維持し、社会を守ることこそが重要だと考えている裁判官も少なくありません。瀬木氏は、こうした「事件処理」偏重の姿勢が、裁判の質を低下させ、真の正義の実現を阻んでいると指摘しています。
深まる司法への不信感
瀬木氏の指摘は、司法制度に対する信頼を揺るがす深刻な問題です。裁判官の知的怠慢は、公正な裁判の実現を阻害するだけでなく、市民の権利や利益を損なう可能性も孕んでいます。
司法の信頼回復のためには、裁判官の意識改革と教育システムの見直しが必要です。多様な視点や深い教養を身につけ、市民の声に真摯に耳を傾ける姿勢が求められます。
瀬木氏の『絶望の裁判所』は、日本の司法制度が抱える問題点を浮き彫りにした重要な一冊です。司法の未来を考える上で、多くの人に読んでいただきたい書籍です。 また、瀬木氏の最新刊『現代日本人の法意識』では、同性婚や共同親権、冤罪、死刑制度など、現代社会における様々な法的問題について、日本人の法意識を分析しながら考察を深めています。こちらも合わせて読んでみることをおすすめします。