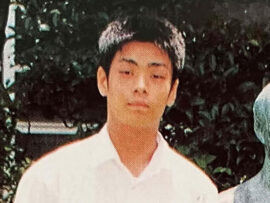大阪・関西万博2025の開幕が目前に迫ってきました。夢洲(ゆめしま)に建設された会場は着々と準備が進められている一方で、チケット販売や準備状況に対する不安の声も聞こえてきます。この記事では、大阪万博を取り巻く現状と、期待と不安が交錯する関西経済の行方について探ります。
チケット販売に見る期待と不安
万博協会は前売りチケットの販売枚数が目標の1400万枚に対し、1000万枚に届きそうだと発表しました。しかし、その内情は必ずしも順風満帆とは言えないようです。協賛企業へのチケット割り当てや、社員だけでなく家族や親族への招待範囲拡大など、集客への苦戦が垣間見えます。ある出展企業の社員は、「ここまで集客力がないイベントに価値があるのか疑問」と不安を口にしています。
 大阪万博会場を視察する石破首相(左)と吉村府知事
大阪万博会場を視察する石破首相(左)と吉村府知事
自民党内からもチケット販売に関する懸念の声が上がっており、特に当日券や紙チケットの必要性を訴えてきた自見英子元万博担当大臣と、吉村知事との意見の相違も報じられています。
経済効果への期待と現実
万博開催による経済効果への期待は大きいものの、現実には厳しい見方をする声も少なくありません。「50円ハイボール」を提供する格安飲食店が人気を集める大阪の現状を踏まえ、鶴橋の飲食店店主は「万博で潤うと期待している店はほとんどない」と語っています。
ミナミの商店街の店員も、「万博の話題は高額なそばやトイレばかりで、庶民には縁遠い」と皮肉を交えて現状を指摘。吉村知事への期待も薄れつつあるようです。
専門家の見解
関西経済研究所の山田一郎氏(仮名)は、「万博開催による経済効果は限定的になる可能性がある」と指摘します。「インバウンド需要の回復は期待できるものの、円安や物価高騰の影響で消費は伸び悩む可能性が高い。また、万博関連の投資効果も一時的なものに留まる可能性がある」と警鐘を鳴らしています。
開催に向けた課題と展望
万博開催まで残りわずか。交通ルールや搬入物の確保など、解決すべき課題は山積しています。万博協会の場当たり的な対応に不安を抱く声も上がっており、開幕までにどこまで準備が整うかが焦点となります。
一方で、万博を契機とした新たな技術やサービスの創出、国際交流の活性化など、将来への期待も残されています。成功に向けて、関係者の一層の努力が求められます。
まとめ
大阪・関西万博2025は、期待と不安が入り混じる中で開幕を迎えます。経済効果への期待がある一方で、チケット販売や準備状況への懸念、そして冷ややかな世論も存在します。万博の成功は、関西経済の活性化だけでなく、日本の未来にも大きな影響を与えるでしょう。今後の動向に注目が集まります。