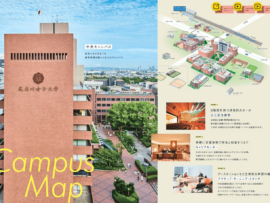昭和という時代、パチンコは庶民の娯楽の王様として君臨し、一大産業へと発展を遂げました。現代では想像もつかないかもしれませんが、当時は店によっては出玉の換金が堂々と行われていた時代もあったのです。今回は、昭和28年(1953年)を舞台に、熱狂の渦に巻き込まれたパチンコの歴史を紐解いていきます。
パチンコ店「ライナー」の青春
昭和28年9月28日、愛媛県新居浜市。パチンコ店「ライナー」(仮名)で働く17歳の河野春江(仮名)は、慌ただしい毎日を送っていました。開店からわずか2ヶ月、連日満員御礼の店内は活気に満ち溢れています。
熱狂の火付け役「機関銃式パチンコ」
その人気の秘密は、当時最新鋭の「機関銃式パチンコ」。従来の「単発式」とは異なり、大量の玉を自動で発射できる画期的なシステムでした。右手一本で操作できる手軽さと、自動で出玉が集まる効率性の高さは、多くのパチンコファンを虜にしました。
 昭和時代の機関銃式パチンコ機を想像したイラスト
昭和時代の機関銃式パチンコ機を想像したイラスト
春江は、玉貸場と出入口の帳場を忙しく行き来しながら、次々と訪れる客に対応していました。「ちょっとおねえさん、早くしてくんない!」とせかす声、タバコの「光」を差し出す主婦の姿…当時のパチンコ店の風景が目に浮かびます。
驚きの売上!一日5000円!?
「機関銃式」の登場により、台当たりの売上は飛躍的に向上しました。1台あたり5000円を売り上げる日もあったといいます。(当時のパチンコ台の価格は数千円程度。昭和27年の大卒国家公務員の初任給は7650円でした。)これは、現代のパチンコ事情と比較しても驚異的な数字と言えるでしょう。 パチンコ史研究家の山田一郎氏(仮名)は、「機関銃式パチンコは、まさに革命的な発明でした。手軽さとスピード感が、当時の若者を中心に爆発的な人気を博したのです」と語っています。
庶民の娯楽から一大産業へ
パチンコは、戦後の日本において庶民の娯楽として急速に普及し、一大産業へと成長を遂げました。「機関銃式」の登場は、その流れをさらに加速させ、パチンコ文化の礎を築いたと言えるでしょう。次回、昭和のパチンコ史をさらに深く掘り下げていきます。
まとめ:昭和のパチンコは熱かった!
今回は、昭和28年のパチンコ店「ライナー」を舞台に、「機関銃式パチンコ」ブームを中心とした当時の様子をご紹介しました。現代とは異なるルールや雰囲気の中で、人々はパチンコに熱狂していたことが伺えます。ぜひ、当時の熱気を想像しながら、次回の記事もお楽しみに!