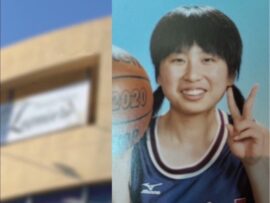不登校児童生徒数は30万人を超え、深刻な社会問題となっています。その解決策として注目されているのが「学びの多様化学校」。今回は、大阪市立心和中学校で新たな一歩を踏み出した一人の少女の物語を通して、多様化学校の意義を探ります。
心和中学校との出会い
家庭では饒舌な15歳の大橋葵さん(仮名)は、学校では言葉を発することができません。場面緘黙という症状に悩まされ、小学校2年生の頃から不登校を繰り返してきました。中学入学後も、言葉を発せないことで疎外感を感じ、再び不登校に。将来への不安や焦燥感に苛まれる葵さんの転機となったのが、大阪市立心和中学校の開校でした。
 リラックスルームでクマのぬいぐるみを抱く葵さん
リラックスルームでクマのぬいぐるみを抱く葵さん
心和中学校は、不登校を経験した生徒のための学校です。葵さんは、再び傷つくことを恐れながらも、「もう一度学校に通いたい」という強い思いから、心和中学校への転校を決意しました。
多様性を受け入れる学び舎
心和中学校では、生徒一人ひとりの状況に合わせた柔軟な指導が行われています。朝、体調不良で起きられない生徒のために、登校時刻は午後。授業時間も短縮され、心身の不調を感じた際には、ソファで休める「リラックスルーム」も用意されています。
文字で繋がるコミュニケーション
葵さんは、言葉の代わりに文字を使って先生や友人とコミュニケーションをとっています。授業中の発言や質問も、ノートに書いて先生に伝えます。最初は戸惑っていた周りの生徒たちも、徐々に葵さんのコミュニケーション方法を理解し、受け入れてくれるようになりました。教育心理学者の山田先生(仮名)は、「文字によるコミュニケーションは、場面緘黙の生徒にとって、自己表現の手段として有効です。周りの生徒たちも、多様なコミュニケーション方法を学ぶことで、共感力や社会性を育むことができます」と指摘しています。
葵さんの変化
心和中学校での学びを通して、葵さんは少しずつ変化を見せています。リラックスルームで過ごす時間も減り、笑顔で登校する日も増えました。葵さんの母親は、「娘が学校に通えるようになっただけでなく、表情も明るくなりました。心和中学校の先生方には感謝しています」と語っています。
未来への希望
心和中学校は、葵さんのような不登校の生徒たちに、学びの場を取り戻すだけでなく、自己肯定感を取り戻す場を提供しています。多様性を尊重し、一人ひとりの個性を大切にする教育は、これからの社会においてますます重要になっていくでしょう。葵さんの物語は、多様化学校の可能性を示すとともに、不登校問題解決への希望を与えてくれます。