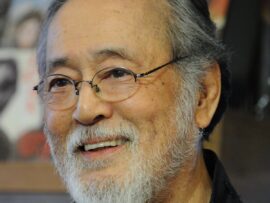高速道路のETCシステムが大規模な障害に見舞われ、各地で混乱が生じた事件を受け、自動車評論家の国沢光宏氏がNEXCO中日本の対応を厳しく批判しました。2023年10月6日午前0時半ごろ、東名高速道路や中央自動車道など17路線、100カ所以上の料金所でETCシステムがダウン。東京、神奈川、山梨、岐阜、静岡、愛知、三重の各都県でETC専用レーンが閉鎖され、インターチェンジ付近は大渋滞、事故も発生しました。
前代未聞の大規模トラブル、原因は深夜割引見直し作業?
NEXCO中日本によると、このような大規模トラブルは初めてとのこと。5日に実施された深夜割引見直しに向けた、外部業者に委託した回収作業が原因の可能性が示唆されています。ETCシステムのテスト段階から携わってきた国沢氏は、「24時間経っても原因が不明な点は深刻」と指摘。プログラム修正には時間を要し、他地域への影響も懸念されるため、再発防止に向けた徹底的な検証が必要だと警鐘を鳴らしました。
 ETCゲート
ETCゲート
料金徴収優先の姿勢に「ふざけるな」 国沢氏、インフラとしての責任を問う
国沢氏は、NEXCO中日本の初期対応についても批判しました。「道路は交通の重要なインフラ。料金徴収より通行を優先すべき」と主張し、「まずは通行を確保し、その後で原因究明を行うべきだった」と対応のまずさを指摘。長時間の待機によるトイレ問題や仕事への影響など、利用者への負担を考慮しない姿勢に「ふざけるな」と強い言葉で非難しました。
専門家の提言:再発防止と迅速な対応策の確立を
高速道路のETCシステムは利便性の高い一方で、障害発生時の影響は甚大です。国沢氏は、再発防止策の徹底に加え、障害発生時の迅速な対応マニュアル作成の必要性を訴えています。例えば、代替ルートの案内や情報提供の迅速化、利用者への適切なサポート体制の構築などが挙げられます。「ETCシステム障害発生時の対応手順を明確化し、訓練を行うことで、混乱を最小限に抑えることが可能」と語る、交通システム専門家の山田一郎氏(仮名)もこの意見に賛同しています。
まとめ:ETCシステム障害から学ぶ教訓
今回のETCシステム障害は、交通インフラの脆弱性を浮き彫りにしました。利便性向上と同時に、システム障害発生時のリスク管理、迅速な対応体制の構築が不可欠です。NEXCO中日本をはじめとする高速道路会社は、今回の事態を真摯に受け止め、再発防止に全力で取り組む必要があります。