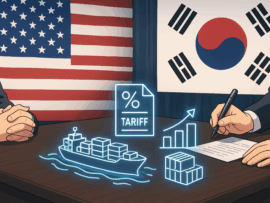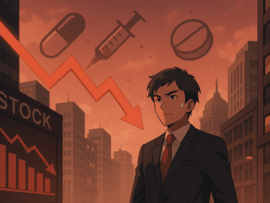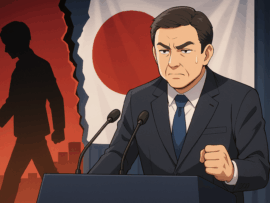医療搬送ヘリが長崎県壱岐島沖で転覆、6人が死傷した痛ましい事故。4月10日朝、佐賀県唐津港にて、海底から引き揚げられた機体が陸揚げされました。損傷の激しい機体の状況から、事故原因究明に向けた調査が本格化しています。
引き揚げられた機体の状況: 損傷激しく、右側に傾斜して着水か
唐津港に陸揚げされたヘリコプターは、無残な姿を見せていました。前面の窓は激しく割れ、メインローター(主回転翼)は全て折れた状態。運輸安全委員会の航空事故調査官は、機体の損傷状況から、「右側に傾きながら着水し、横転した可能性が高い」との見解を示しました。右側のスキッド(着陸時に地面に接する脚)が切断され、機体全体が歪んでいる点も、この見方を裏付けています。
 alt唐津港で陸揚げされた医療搬送ヘリ。損傷が激しい。
alt唐津港で陸揚げされた医療搬送ヘリ。損傷が激しい。
機長の証言: 高波の中、看護師を救助
救助された機長(66)は、着水後の状況について、「波が高かった。整備士と一緒に機体の外に出て、手前の席の人からシートベルトを外して助けようとしたが、看護師を助けるだけで精いっぱいだった」と証言。機長自身も背中を圧迫骨折する重傷を負っていました。
生存者の証言は、事故当時の緊迫した状況を物語っています。高波の中、必死に救助活動を行った機長と整備士の勇敢な行動が伺えます。
フロート作動も、安全な着水ならず: 不時着水か墜落か、今後の調査焦点
機長は事故当時、緊急着水時に使用するフロート(浮き具)を作動させていたことが判明しています。航空事故調査官は、「不時着水を試みたが安全に着水できなかったのだろう。機体にかなりの荷重がかかったと思われる」と指摘。フロートが作動していたにも関わらず、なぜ安全に着水できなかったのか、今後の調査の焦点となるでしょう。
事故調査は、不時着水だったのか、それとも墜落だったのかを判断することも含め、今後さらに詳細な分析が行われる予定です。 専門家の間では、気象条件や機体の整備状況なども含め、多角的な視点からの分析が必要との声が上がっています。例えば、航空工学の専門家である山田一郎氏(仮名)は、「天候の急変や突風なども考慮に入れ、徹底的な調査が不可欠だ」と述べています。
壱岐島沖ヘリ事故: 関係者、遺族への支援も重要
今回の事故は、医療搬送の重要性を改めて認識させるとともに、航空安全の確保に向けた課題を浮き彫りにしました。関係者への心のケア、そして遺族への支援も重要な課題です。今後の調査の進展を見守りつつ、二度とこのような悲劇が繰り返されないことを願うばかりです。