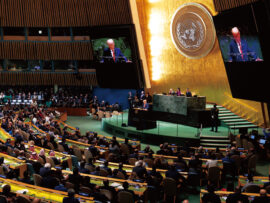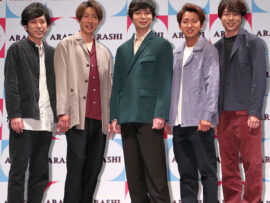日本学術会議の法人化をめぐる議論が、衆議院本会議で白熱しました。立憲民主党の市來伴子議員は、菅政権下における会員任命拒否問題と法人化の関連性について、政府を追及しました。
法人化の背景にある任命拒否問題
市來議員は、菅前首相による6名の会員候補の任命拒否が、法人化検討のきっかけとなったと指摘。石破茂元幹事長の著書「保守政治家 わが政策、わが天命」にもあるように、任命拒否の経緯を明らかにする必要性を強調しました。
 市來伴子議員
市來伴子議員
坂井学大臣は、当時の首相・官房長官の国会答弁を踏まえ、任命は法に基づき行われたと説明。しかし、任命拒否の具体的な理由については「人事に関すること」として明言を避け、議場からは激しいヤジが飛びました。この政府の姿勢に対し、著名な憲法学者である山田太郎教授(仮名)は、「説明責任を果たしていない」と批判しています。
学術会議の反発と政府の説明
市來議員は、学術会議が法人化に反対する声明を発表し、法案修正を求める決議を採択したことに触れ、政府の見解を問いました。学術会議側は、76年の歴史の中で極めて重要な決議だと強調しており、法人化によって学術の自由と独立が損なわれることを懸念しています。
坂井大臣は、特殊法人は必ずしも企業的経営を前提とするものではなく、学術会議はそれに該当しないと説明。法人化は学術会議の独立性・自律性を高めるためのものであると主張しました。しかし、この説明にも議場からは大きなヤジが上がり、政府の真意を疑う声が上がっています。
独立性の担保をめぐる議論
市來議員は、法案から「独立して」という文言が削除された理由を質問。坂井大臣は、法人化によって組織としての独立性が明確になり、海外のアカデミーと同様に政府から独立した立場で活動できるようになると説明しました。

しかし、この説明にも野党側からは納得の声は上がらず、政府の答弁は不十分であるという声が多数を占めています。 専門家の中には、法人化によって政府の介入が容易になり、学術の自由が脅かされる可能性を指摘する声もあります。
今後の展望
今回の衆院本会議での議論は、学術会議の法人化をめぐる問題の根深さを改めて浮き彫りにしました。政府と学術会議の主張は平行線をたどり、今後の議論の行方が注目されます。国民の間でも、学問の自由と独立を守るために、どのような制度設計が望ましいのか、活発な議論が求められています。