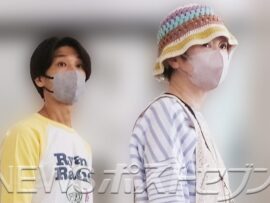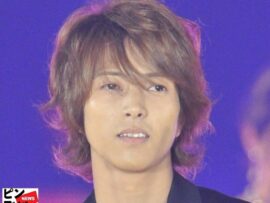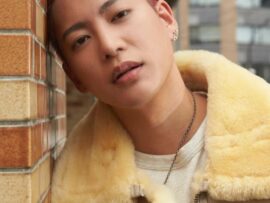江戸時代を彩る二人の偉人、杉田玄白と平賀源内。NHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」でも描かれた二人の関係性、友情の裏にはどのような感情が隠されていたのでしょうか?本記事では、マルチな才能で活躍した平賀源内と、蘭学に情熱を注いだ杉田玄白の交流、そして玄白が源内に抱いていたかもしれない羨望の念について探っていきます。
マルチクリエイター平賀源内と蘭学者杉田玄白:二人の出会い
「べらぼう」では、安田顕さん演じる平賀源内と山中聡さん演じる杉田玄白の交流が描かれています。史実においても二人は親交が深く、互いを認め合う仲でした。源内は本草学、地質学、蘭学、殖産事業、戯作、浄瑠璃、俳諧、蘭画、発明など、多岐にわたる分野で才能を発揮したマルチクリエイター。一方、玄白は『解体新書』の翻訳で知られる蘭学者であり、小浜藩医という立場にもありました。
 杉田玄白像
杉田玄白像
異なる生き方:自由な源内と制約のある玄白
自由奔放に様々な分野で活躍する源内に対し、玄白は藩医としての立場や社会的な制約の中で生きていました。ドラマでも描かれているように、玄白は源内の自由な活動を羨ましく思っていたのかもしれません。「エレキテル」に対する源内の言動にため息をつく玄白の姿からは、彼の複雑な心境が垣間見えます。
医学への情熱と『解体新書』の誕生
玄白は享保18年(1733)、江戸牛込矢来(現在の東京都新宿区)に小浜藩医の息子として生まれました。生後すぐに母を亡くすという悲しい出来事を経験しますが、父の跡を継ぎ医学の道を志します。そして前野良沢らと共にオランダの医学書『ターヘル・アナトミア』の翻訳に取り組み、安永3年(1774)に『解体新書』を出版。日本の医学史に大きな功績を残しました。
源内への憧憬:自由な探求心への羨望
当時の蘭学研究は困難を極め、多くの制約がありました。一方で、源内は自由に研究を行い、様々な分野で成果を上げていました。玄白は源内の旺盛な好奇心と探求心、そして自由な生き方に憧れを抱いていたのではないでしょうか。

友情と羨望:二人の関係性の考察
二人の関係は友情でありながらも、玄白の中には源内への羨望の念も存在していたと考えられます。「非常の人」と源内を評した玄白の言葉には、賞賛と共に、自身とは異なる生き方への複雑な感情が込められているように感じられます。 江戸時代の著名な料理研究家、架空の「江戸川美食斎」は二人の関係について、「玄白は源内の才能に嫉妬していたのではなく、彼の自由な生き方に憧れていたのだ」と述べています。
時代を超える友情:現代社会への示唆
二人の物語は、現代社会を生きる私たちにも多くの示唆を与えてくれます。異なる個性や才能を持つ者同士が、互いに認め合い、刺激し合うことで、新たな価値を創造していくことの大切さを教えてくれるのではないでしょうか。
まとめ:二人の偉人が遺したもの
杉田玄白と平賀源内。二人の関係は、友情、尊敬、そして少しの羨望が入り混じった複雑なものでした。しかし、互いの才能を認め合い、それぞれの分野で活躍した彼らの功績は、現代の私たちにも多くの inspiration を与えてくれます。