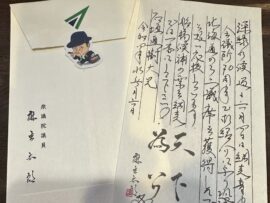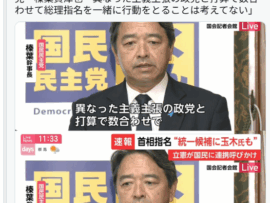日本の年金制度に大きな変化が訪れています。2025年4月から、厚生労働省が発行する「ねんきん定期便」に、事業主も従業員と同額の厚生年金保険料を負担している事実が明記されることになりました。これは、長年年金制度の課題を指摘してきた専門家や、将来への不安を抱える現役世代にとって、大きな一歩と言えるでしょう。
「ねんきん定期便」改訂の背景:25年間の沈黙を破る真実
これまで「ねんきん定期便」には、従業員が支払う厚生年金保険料のみが記載され、事業主負担分は明示されていませんでした。経済ジャーナリストの湯浅大輝氏は、この問題を25年前から指摘してきた作家の橘玲氏にインタビューを行いました。橘氏は、多くのメディアがこの事実を取り上げなかったことに疑問を呈し、現役世代が「厚生年金の不都合な真実」に気づき始めたことが、今回の改訂の背景にあると分析しています。
 ねんきん定期便のイメージ
ねんきん定期便のイメージ
年金制度の「幻想」:現役世代の負担はどこまで?
橘氏は、年金制度が現役世代から高齢者への「仕送り」システムであることを指摘し、少子高齢化が進む中で、このシステムの持続可能性に疑問を投げかけています。2007年の「消えた年金問題」以降、年金制度への不安が高まり、厚労省は「ねんきん定期便」を通して、将来受け取れる年金の見込み額を提示するようになりました。しかし、事業主負担分を明示しなかったことで、現役世代の負担の実態が隠蔽されていたと橘氏は主張します。
「人生100年時代」の現実:年金だけで安心できるのか?
「人生100年時代」と言われる現代において、20歳から60歳までの40年間の積み立てで、100歳までの40年間を安心して暮らせるという考えは現実的ではないと橘氏は指摘します。 年金制度は、現役世代が将来安心して老後を迎えられるという「幻想」を維持するために、事業主負担分を明示してこなかった可能性があると、同氏は分析しています。
年金制度の未来:私たちは何をすべきか?
今回の「ねんきん定期便」の改訂は、年金制度の透明性を高めるための重要な一歩です。現役世代は、自身の年金保険料の使い道や、将来受け取れる年金額について、より正確な情報を得ることができるようになりました。 しかし、年金制度の持続可能性や、老後の生活設計については、引き続き議論が必要です。 私たち一人ひとりが年金制度の現状を理解し、自身の老後について真剣に考えることが、より良い未来を築くために不可欠です。