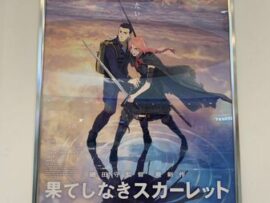熊本地震から9年が経ちましたが、熊本県民にとって地震への不安は未だ消えません。特に、活断層である日奈久断層帯の活動は依然として活発で、専門家はさらなる大地震発生の可能性を指摘しています。この記事では、日奈久断層帯の現状と地震対策の重要性について詳しく解説します。
日奈久断層帯の現状:専門家の見解
九州大学地震火山観測研究センターの松本聡センター長によると、日奈久断層帯の活動は依然として活発であり、特に南側の区間は注意が必要とのことです。熊本地震では、布田川断層帯と日奈久断層帯の北側が大きくずれ動きましたが、南側はエネルギーが蓄積されたままの状態です。周辺地域では、体に感じない小さな地震も含め、年間約4400回もの地震が観測されており、その多くは日奈久断層帯の西側で発生しています。
 alt: 九州大学地震火山観測研究センターが設置した地震計のデータを示す地図。日奈久断層帯周辺で多数の地震が観測されている。
alt: 九州大学地震火山観測研究センターが設置した地震計のデータを示す地図。日奈久断層帯周辺で多数の地震が観測されている。
地震活動の活発化:M7クラスの地震発生の可能性も
2024年3月18日には、日奈久断層帯南側周辺で最大震度4の地震が発生しました。これは、この地域での地震活動が依然として活発であることを示しています。松本センター長は、この状況が続けば、さらに大きな地震が発生する可能性もあると警鐘を鳴らしています。
“Sランク”の脅威:日奈久断層帯の地震発生確率
政府は、日奈久断層帯の南側を地震発生の切迫度が最も高い「Sランク」に指定しています。「Sランク」とは、今後30年以内の地震発生確率が3%以上の活断層のことです。日奈久断層帯の「日奈久区間」ではマグニチュード7.5、「八代海区間」ではマグニチュード7.3の地震が想定されており、これは熊本地震の本震に匹敵する規模です。
津波への備えも重要:八代海沿岸地域への影響
特に、八代海区間で地震が発生した場合、津波がすぐに到達する可能性があります。そのため、沿岸地域にお住まいの方は、避難経路や避難方法を事前に確認しておくことが重要です。
地震への備え:今できることから始めよう
熊本県には、日奈久断層帯以外にも南海トラフ巨大地震の発生リスクも存在します。松本センター長は、「地震はいつ起こるかわからない。だからこそ、冷静にできる準備をしておくことが大切」と述べています。
alt: 熊本県内の活断層を示す地図。日奈久断層帯と布田川断層帯の位置が示されている。
家具の固定、非常持ち出し袋の準備など、できることから始めましょう
家具の固定や非常持ち出し袋の準備など、今できることから始めましょう。家族や地域で防災について話し合い、万が一の事態に備えることが大切です。
まとめ:日奈久断層帯への警戒と地震対策の徹底を
日奈久断層帯は、依然として活動が活発であり、大地震発生の可能性は否定できません。この記事をきっかけに、改めて地震への備えを見直し、家族や地域で防災意識を高めていきましょう。