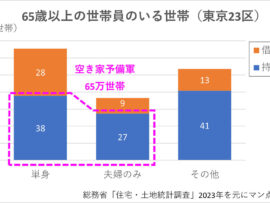日本郵便は、ドライバーへの法定点呼が適切に行われていなかった問題で、全国約3200局のうち、75%にあたる2391局で不適切な点呼があったと発表しました。長年にわたり常態化していた可能性も示唆され、経営ガバナンスの欠如が浮き彫りとなっています。jp24h.comでは、この問題の背景、影響、そして今後の対策について詳しく解説します。
点呼不正の実態:氷山の一角か?
2025年4月23日、日本郵便の千田哲也社長は記者会見で謝罪し、「関係の皆様に大変なご心配をおかけした」と陳謝しました。点呼と運送業務はセットであるべきにも関わらず、会社全体の意識が希薄化していたことが今回の事態を招いたと説明。書類上は適切な点呼が行われていたように装い、実態は放置されていたケースが多数あったことを認め、「書類さえ整っていれば良いという風潮が蔓延し、ガバナンスが欠如していた」と反省の弁を述べました。
 alt=日本郵便の千田哲也社長が記者会見で謝罪している様子
alt=日本郵便の千田哲也社長が記者会見で謝罪している様子
不適切な点呼が始まった時期は「不明」としながらも、「かなり昔から行われていたのではないか」との見方を示し、現場での慣行化を指摘しました。さらに、今回の調査結果が「氷山の一角」である可能性も示唆し、全社を挙げて徹底的な調査を行う方針を表明しています。
点呼不正問題の発覚から現在までの経緯
この問題は、2024年5月に横浜市の郵便局で配達員が点呼を受けずに飲酒運転を行い、11日後に警察に通報されたことが発端となりました。その後、兵庫県の郵便局で数年にわたる点呼未実施が発覚し、近畿支社管内の約8割で同様の不正が明らかになりました。

本社は2024年5月30日に全国の郵便局に点呼徹底を通知しましたが、効果は薄く、2025年2月には東京都内でも飲酒運転事案が発生。この事案は公表されませんでした。3月に入り、朝日新聞の報道によって不適切点呼の問題が明るみに出たことで、本社は記者会見を開き謝罪しました。
その後も、横浜での飲酒運転や都内の飲酒事案が朝日新聞の報道で次々と発覚。日本郵政の増田寛也社長は報告の遅れを批判しました。そして4月23日、ついに全国調査の結果が公表され、その深刻さが改めて認識されることとなりました。
今後の対策と課題
日本郵便は、再発防止策として、点呼システムの見直しや社員教育の徹底を図るとしています。しかし、長年にわたり根付いてきた不正慣行を根絶するには、単なるシステム変更や教育だけでは不十分です。現場の意識改革、そして経営陣の強いリーダーシップが不可欠となるでしょう。
運輸安全マネジメントの専門家である山田太郎氏(仮名)は、「点呼はドライバーの安全を守るだけでなく、社会全体の安全を守る上でも非常に重要です。今回の問題は、日本郵便の安全意識の低さを露呈したものであり、徹底的な原因究明と再発防止策の実施が求められます」と指摘しています。
まとめ
今回の点呼不正問題は、日本郵便の信頼を大きく損なう結果となりました。再発防止に真摯に取り組み、信頼回復に努めることが求められます。jp24h.comでは、引き続きこの問題の進展を追っていきます。