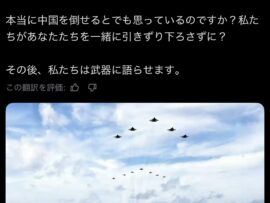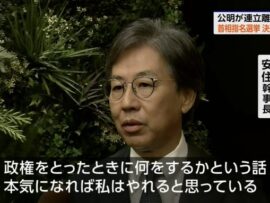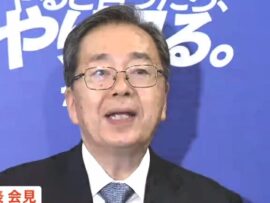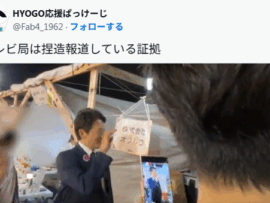江戸時代中期、吉原で生まれ育ち、様々な分野で才能を発揮した蔦屋重三郎。NHK大河ドラマ「べらぼう」では、彼の波瀾万丈な人生が描かれています。今回は、ドラマを通して、重三郎と深く関わったもう一人の異才、平賀源内の人生に焦点を当て、その才能と悲劇、そして現代にも通じる苦悩について探っていきます。
多才な才能を発揮した平賀源内
「べらぼう」第16回「さらば源内、見立は蓬莱」では、蔦重が源内のもとを訪ねるシーンが印象的でした。源内といえば、エレキテルの開発や蘭学、戯作など、多岐にわたる分野で活躍したマルチな才能の持ち主として知られています。当時の常識にとらわれない自由な発想と行動力で、江戸の人々を驚かせ続けたのです。
 平賀源内像
平賀源内像
エレキテルと蘭学への貢献
源内は、静電気を発生させる装置「エレキテル」を日本に紹介し、改良を加えることで普及に貢献しました。また、蘭学にも精通し、西洋の知識を積極的に吸収することで、日本の科学技術の発展に尽力したのです。 江戸時代の科学技術史において、源内の功績は計り知れません。京都大学名誉教授の中野三敏先生も、源内を「江戸時代のレオナルド・ダ・ヴィンチ」と評しています。
平賀源内が開発したエレキテル
報われなかった才能と悲劇的な結末
しかし、その才能にもかかわらず、源内の人生は決して順風満帆ではありませんでした。「べらぼう」では、田沼意次との確執が描かれていますが、実際にも源内は様々な困難に直面し、晩年は悲劇的な最期を迎えることになります。
『放屁論後編』に垣間見える源内の苦悩
源内が著した『放屁論後編』には、彼自身の苦悩が吐露されています。作中で、源内は自身を「山師」と揶揄する世間の声に反論し、真摯に日本のために尽くそうとしているにもかかわらず、理解されない frustration を表現しています。 食通としても知られた源内。料理研究家の土井善晴先生は、源内の料理への探究心は、彼の多様な才能の表れであり、現代の食文化にも影響を与えていると述べています。
現代社会にも通じる源内の苦悩
源内の苦悩は、現代社会にも通じるものがあります。新しい発想や挑戦がなかなか受け入れられなかったり、努力が報われなかったりする経験は、多くの人が共感できるのではないでしょうか。源内の人生は、私たちに才能の大切さと同時に、それを活かすことの難しさ、そして周囲の理解の重要性を教えてくれます。
まとめ:平賀源内から学ぶこと
平賀源内は、江戸時代を代表するマルチな才能の持ち主でした。しかし、その才能は必ずしも報われるとは限らず、悲劇的な結末を迎えることになります。彼の生涯は、私たちに才能の活かし方、そして周囲の理解の大切さを教えてくれます。大河ドラマ「べらぼう」を通して、改めて平賀源内の功績と苦悩に思いを馳せ、現代社会における才能の在り方について考えてみてはいかがでしょうか。