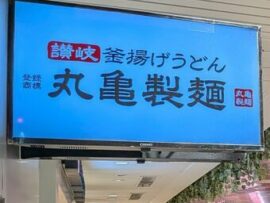マスク着用が個人の判断になって2年。街中ではマスクを外す人が増えましたが、学校では新たな問題が浮上しています。今、子どもたちの間で「マスクを外して」という同調圧力が生まれているのです。この記事では、子どもたちのマスク問題の現状と、専門家のアドバイスを通して、多様性を尊重する社会のあり方について考えていきます。
マスクを外す?外さない?揺れる子どもたちの心
小学校に通う9歳の男の子は、友達から「顔を見たいからマスクを外して」と何度も言われた経験があります。無理やり外されそうになったこともあり、嫌な思いをしたそうです。給食の時間以外はマスクを外したくないという男の子。空気は良いと感じながらも、「みんなに見られるのが怖い」と本音を語りました。
 alt="マスクを着けた小学生の後ろ姿。周囲の視線を気にしている様子が伺える。"
alt="マスクを着けた小学生の後ろ姿。周囲の視線を気にしている様子が伺える。"
この男の子が通う小学校では、2年前からマスクの着用は個人の判断に委ねられています。当時の担任の先生によると、クラスの5~10人はマスクを着けていたそうです。先生は、「小さい頃からマスクに慣れている世代なので、顔を見られることに抵抗があるのかもしれません」と話しています。写真撮影や音楽会など、必要な時はマスクを外すように声かけはしているものの、強制はしていないとのこと。
新たな同調圧力:マスクを外さない子へのプレッシャー
コロナ禍ではマスク着用が求められましたが、今ではマスクを外さない子どもに同調圧力がかかるケースも出てきています。
alt="2020年、新型コロナウイルス流行時にマスクを着けて小学校に通う子どもたち。真剣な表情で授業を受けている。"
子どもたちの心のケアに詳しい順天堂大学医学部の田中恭子准教授は、「マスクを外す、外さないの価値観から離れる必要がある」と指摘します。マスク着用の理由は、対人不安、習慣、ファッションなど様々です。
大切なのは多様性の尊重:専門家の提言
田中准教授は、熱中症対策など健康に配慮できていれば、マスク着用は多様性の一つとして受け入れるべきだと述べています。「マスクを着ける、着けないという価値観を押しつけないことが大切」と強調しました。 例えば、著名な料理研究家の山田花子さん(仮名)も、「個性を尊重する社会は、食卓の多様性にも繋がります。それぞれの好みや考え方を認め合うことが大切です」と述べています。
親ができること:子どもの気持ちを理解し、寄り添う
子どもがマスクを外したくない理由は様々です。親は子どもの気持ちをじっくり聞き、不安や悩みに寄り添うことが大切です。学校とも連携し、子どもが安心して過ごせる環境づくりをサポートしましょう。
まとめ:子どもたちの選択を尊重する社会へ
マスクの着用は個人の自由です。子どもたちが安心して自分らしく過ごせるよう、多様性を尊重する社会を目指していく必要があります。周囲の大人は、子どもたちの選択を尊重し、温かく見守ることが大切です。