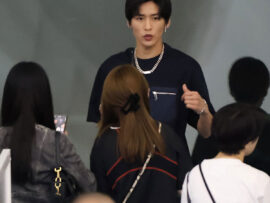今年6月17日、X(旧Twitter)に投稿された「私達は週6回80kgの荷物を背負って片道10kmの道のりを歩きます。はじめまして、歩荷です。」というポストが、インターネット上で大きな反響を呼びました。過酷な自然環境の中で、人と自然の共存を支える重要な役割を担う「歩荷(ぼっか)」という職業。その知られざる実態と、彼らが山小屋の生命線としていかに不可欠な存在であるかを探ります。
歩荷とは?知られざるその仕事の全貌
「歩荷」とは、登山道や山間部など、車両が入れない場所に荷物を運ぶ専門の担ぎ手のことです。かつては日本全国に存在したこの職業ですが、現代において専業として活動する人はごくわずかになりました。そのような中で、福島県、新潟県、群馬県の三県にまたがる広大な尾瀬エリアで、11年間も歩荷として活動を続ける萩原雅人さん(32歳)に、この特別な仕事について話を聞きました。
萩原さんの仕事は、主に山小屋への物資供給です。保存が利く物資は月に一度ヘリコプターでまとめて運ばれますが、鮮度の維持が不可欠な新鮮な野菜、生鮮食品、飲料などは、歩荷が自らの足で運搬しています。尾瀬エリアでは現在、11の山小屋と契約を結んでおり、これらの小屋に日々、必要な物資を届けています。
尾瀬の歩荷が語る、日々の業務と過酷な現実
尾瀬の歩荷たちが直面する日常は、想像以上に過酷でありながら、同時に強い使命感に支えられています。萩原さんは、この仕事の具体的な側面を詳細に語ってくれました。
山小屋を支える「命の運搬人」の役割
歩荷の出発地点は、尾瀬の玄関口である鳩待峠(はとまちとうげ)です。ここが拠点であり、同時に物資運搬のゴール地点でもあります。最も近い目的地である至仏山山荘(しぶつさんさんそう)の山ノ鼻地区までは片道3.3kmと比較的距離が短いため、一日に二往復することもあります。一方で、最も遠い温泉小屋や見晴地区の小屋までは片道12kmにも及びます。平均すると、一日に約9kmの道のりを歩くことになります。
運搬する荷物の重さも尋常ではありません。一度に運ぶ荷物の平均は約75kgに達し、多い時にはなんと180kgもの荷物を背負って歩く日もあるといいます。これらの重い荷物は、ただ運ぶだけでなく、安全かつ効率的に運搬できるよう、入念な荷造りが必要となります。

距離と重さ、そして時間の戦い
歩荷の出発はいつも朝8時頃です。各山小屋が昼食を用意してくれているため、目標は正午に山小屋に到着すること。二往復する日も、二回目の荷物を昼食時までに届けるよう調整します。早く着きすぎると山小屋の迷惑になるため、ベテランは到着時間を逆算し、途中で時間を調整することもあるそうです。下山して勤務を終えるのは、だいたい午後3時頃となります。体力だけでなく、時間管理の感覚も問われる仕事です。
少数精鋭、尾瀬を支える歩荷たちの現状
現在、尾瀬で活動している歩荷は7人です。最年長は49歳で、歩荷歴28年の大ベテラン。萩原さんは11年目で三番手のキャリアを持ちます。彼らの下には、5年目、2年目、そして1年目の若手から中堅まで、年齢もキャリアも実に多様なメンバーが揃っています。それぞれの経験と知識が、過酷な環境での作業を支えています。
過酷な仕事に見合う報酬体系とは
歩荷の給与体系は、運搬する荷物の重さと距離によって決まる歩合制です。例えば、3.3kmのコースでは1kgあたり約85円、9kmのコースでは1kgあたり約165円が報酬となります。9kmのコースで75kgの荷物を運んだ場合、一日の運搬で約1万2千円から1万3千円の収入になる計算です。運搬量と距離に応じて収入も変動するため、まさに体力と努力がそのまま報酬に直結するシステムです。
 重い荷物を背負い、山道を歩く歩荷の姿
重い荷物を背負い、山道を歩く歩荷の姿
週6勤務が示す、プロフェッショナルな覚悟
冒頭で話題になったポストにもあったように、歩荷は基本的に週6日勤務です。月曜日が定休日となっています。今年のシーズンは、常駐隊として別の山域に行くメンバーもいるため、残りの歩荷たちが協力し合い、日々の運搬業務を回しています。5月中旬には10月までのシーズン全体のスケジュールが発表され、誰がどの小屋に行くかが週単位で細かく組まれ、そのローテーションを毎週着実にこなしていくのです。これは、山小屋の運営と登山者の安全を支えるという、彼らのプロフェッショナルとしての強い覚悟を示しています。
結論:人と自然を結ぶ歩荷の未来
歩荷の仕事は、単に荷物を運ぶだけではありません。それは、都市部から離れた山岳地帯に暮らす人々や、登山に訪れる人々の生活を支える「命の運び手」であり、人と自然の間に立つ重要な架け橋です。彼らの地道で過酷な労働がなければ、尾瀬のような国立公園内の山小屋は、食料や必需品を安定的に供給することができず、その維持は困難になるでしょう。
現代社会において、効率化や機械化が進む中で、人力による運搬という伝統的な職業は貴重な存在です。歩荷たちは、厳しい自然と向き合いながら、山岳文化と環境保全の一翼を担っています。彼らの存在は、私たちに、便利さの裏側にある努力や、自然との共存の大切さを改めて教えてくれます。今後も、尾瀬の美しい自然と、そこを訪れる人々、そして山小屋の営みを支え続ける歩荷たちの活躍に注目が集まることでしょう。