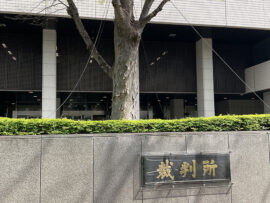近年、コメの価格高騰が家計を圧迫しています。政府は米不足を否定していますが、消費者の間では不安が広がっています。一体何が起きているのでしょうか?この記事では、専門家の意見やコメ生産者の声を交え、コメを取り巻く現状と今後の見通しについて詳しく解説します。
なぜコメの価格は下がらないのか?
コメの価格高騰の背景には、複数の要因が絡み合っています。宮城大学名誉教授の大泉氏によると、2023年の猛暑によりコメの白濁(品質不良)が増加し、主食用米が大幅に減少したことが大きな原因の一つです。実際、2023年6月時点で主食用米は約40万トン減少しています。
 コメの生育状況をドローンで確認
コメの生育状況をドローンで確認
さらに、カメムシの異常発生も深刻な問題となっています。カメムシはコメの品質を低下させるだけでなく、収穫量にも大きな影響を与えます。これらの要因が重なり、コメの供給量が減少しているのです。
生産者の声:値上げは本当に不当なのか?
農業法人『トゥリーアンドノーフ』の徳本修一氏は、長年のコメ生産者として現状を危惧しています。徳本氏によると、猛暑やカメムシ被害の影響は政府の発表よりも深刻であり、実際の収穫量は作況指数よりもはるかに少ないといいます。
「コメの価格は長年据え置かれ、生産コストの上昇に全く見合っていませんでした。肥料代、種代、機械代などは上がり続けているにもかかわらず、米価は上がらず、多くのコメ農家が廃業に追い込まれました。お茶碗一杯25円だったものが40〜50円になったとはいえ、農家の手間を考えれば適正価格と言えるのではないでしょうか。」と徳本氏は訴えます。
消費者の理解が必要
コメの価格高騰は、消費者にとって大きな負担となります。しかし、生産者の苦労や現状を理解することで、より建設的な議論ができるはずです。コメ農家が持続可能な農業を続けられるよう、適正な価格設定と流通システムの改善が求められています。
今後の見通しと課題
コメの価格高騰は、今後も続く可能性があります。気候変動の影響や生産者の高齢化など、コメを取り巻く環境は厳しさを増しています。持続可能なコメ生産を実現するためには、生産者への支援策の強化、新品種の開発、流通システムの効率化など、多角的な取り組みが必要です。
食料安全保障の観点からも、国産米の安定供給は極めて重要です。消費者、生産者、政府が一体となって、この課題に取り組む必要があります。
まとめ
コメの価格高騰は、猛暑やカメムシ被害による供給量の減少、そして長年の低米価による生産コストの増加が主な原因です。消費者は、生産者の現状を理解し、持続可能なコメ生産のために協力していくことが大切です。