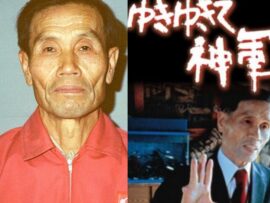近年、プロ野球の地方開催が激減している現状をご存知でしょうか?かつては地方球場での試合も多く、地域住民にとってプロ野球観戦の貴重な機会となっていましたが、今ではその数は大きく減少しています。一体なぜこのような変化が起こっているのでしょうか?この記事では、その背景にある経済的な理由や球団の戦略、そして地方開催の未来について深く掘り下げていきます。
地方開催減少の背景:儲からない現実
1989年には95試合もあった地方開催が、2022年には26試合にまで減少しました。この劇的な変化の理由は、ズバリ「経済合理性」、つまり「儲からないから」です。元ロッテ投手であり、ソフトバンク球団幹部、そして現在は桜美林大学教授を務める小林至氏も自身のYouTubeチャンネル「小林至のマネーボール」でこの点について解説しています。
 桑田真澄プロ初ホームラン
桑田真澄プロ初ホームラン
かつては多くの球団が球場を間借りしていましたが、現在では多くの球団が本拠地球場の運営権を持ち、独自のビジネスを展開しています。本拠地球場での試合は、球団にとって大きな収益源となっています。小林氏によると、本拠地開催の興行収入は1試合あたり少なくとも5000万円にのぼる一方で、地方開催は2000~3000万円程度にとどまるそうです。この収益の差が、地方開催減少の大きな要因となっているのです。
地方球場と本拠地球場の格差:設備投資と演出の進化
地方開催が減少しているもう一つの理由は、地方球場と本拠地球場の設備格差です。近年、多くの球団が本拠地球場に大規模な投資を行い、LEDビジョンや最新の演出設備を導入しています。アーティストのコンサートにも匹敵するような演出は、ファンにとって大きな魅力となっています。しかし、地方球場ではこのような設備投資が難しく、本拠地球場と同じレベルの試合体験を提供することが困難になっています。
さらに、選手のトレーニング環境も地方球場では問題となる場合があります。最新のトレーニング設備を備えた本拠地球場と比較すると、地方球場の設備は劣っている場合が多く、選手のコンディション調整にも影響を与える可能性があります。
地方開催の未来:球団の努力と新たな可能性
地方開催の未来はどうなるのでしょうか?小林氏は「なおさら難しくなる」と指摘しています。しかし、西武の大宮開催や楽天の東北遠征のように、本拠地以外での試合開催に積極的に取り組んでいる球団もあります。これらの球団の努力は、地方の野球ファンにとって大きな希望と言えるでしょう。
今後の地方開催は、球団の努力に加えて、地域活性化との連携や新たなビジネスモデルの構築など、様々な可能性を模索していく必要があるでしょう。地方開催の減少は、プロ野球界にとって大きな課題であり、球団、地域、ファンが一体となって解決策を探っていくことが重要です。
例えば、地域特産品とのコラボレーションや、地元企業との連携によるイベント開催など、地域経済を活性化させる取り組みと組み合わせることで、地方開催の魅力を高めることができるかもしれません。また、オンライン配信技術の進化を活用し、地方球場での試合をより多くの人に届けることで、新たなファン層の獲得にも繋がる可能性があります。
プロ野球の地方開催は、単なる試合だけでなく、地域に活気をもたらす貴重な機会です。未来に向けて、地方開催の価値を再認識し、より良い形での存続を目指していく必要があるでしょう。