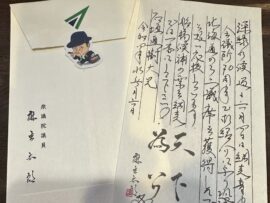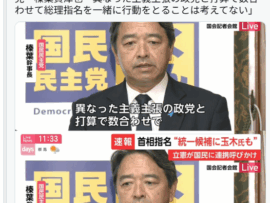[ad_1]
埼玉にもある紙文化と非ネット社会
コロナ騒動を機に、埼玉県内のベッドタウンにある団地に引っ越した67歳のベテラン記者・S氏は、団地の自治会で書記を依頼されている。原稿の執筆経験が豊富なS氏はてっきり、「面倒で誰もやりたくない仕事だから、周りの人たちが僕に仕事を回そうとしたのかな」と思ったというが、実態はそうではなかったのである。
「数十人の住人のなかに、パソコンを満足に扱える人がほぼいなかったのです。自治会の集会室に行ったらコピーの複合機が置いてありました。紙に連絡事項を書いて、コピーして配布するスタイルをいまだに続けていたんですよ。例えば、“草取りをやります”という行事の連絡も、LINEで回せばいいのにいまだに回覧板なのです。信じられますか? 令和の時代なのに、やっていることがほぼ昭和と変わらないのです」
そうS氏が指摘するように、自治会の連絡手段はことごとく“紙”であり、緊急を要する連絡は“電話”なのである。そして、さらに緊急の相談事があると、ノーアポで直接部屋まで関係者がやって来るのだという。実は、S氏に取材中、タイミングよく自治会の役員から電話がかかってきた。20分にも及んだ電話は用件だけで終わるのではなく、雑談もかなりの時間を占めていた。
自治会の会費も集金して回っている
S氏が住む団地は昭和の時代に建設されたものだが、そのなかにはそっくりそのまま昔の団地文化が現存し、稼働しているのだ。しかも、他にもS氏の団地には昭和の文化が残っているのだという。その筆頭格が、自治会費を集金するシステムだ。
「自治会費は部屋を回って、現金で直接集金しています。それを手作業で数え、現金のまま銀行に持って行き、預けるスタイルをいまだに続けているんですよ。ひっくり返りそうになりました。会費なんて引き落としにするか振り込みにすればいいのに、手間をかけて手仕事で集めているんです。私は“振り込みにしたら”と提案したことがありますが、それを聞いても大半の人がきょとんとしていました。
スマホのアプリやパソコン上からもいくらでも送金できる時代なのに、うちの近所にある銀行のATMにはしばしば長蛇の列ができます。観察していると、わざわざ現金を用意してATMから送金している高齢者をよく目にします。口座残高から直接振り込めるはずなのですが、教わる機会がないのか、現状で不便を感じないのか、現金主義なのです」
ちなみに、千葉県内在住のS氏の知り合い(70代で一軒家住まい)の町内の自治会でも、やはり回覧板と自治会費の現金集金が継続されているそうだ。自治会費を集める当番になると、1年間、一軒ずつ集金して回ることになる。夏場は暑いし、住人が不在のことも多いだろう。実際、「死ぬほど面倒くさい」そうだが、自治会ではこのシステムを変える予定はないそうだ。
[ad_2]
Source link