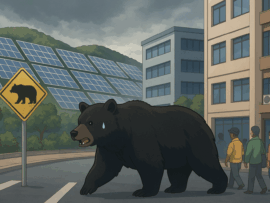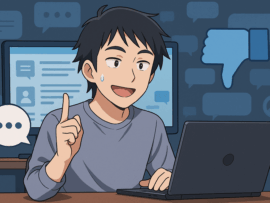[ad_1]
小さく生まれる赤ちゃんが、高齢出産や不妊治療、早産の増加などにより増えている。厚生労働省の「人口動態統計特殊報告(令和3年度)」によると、この45年ほどで極低出生体重児(1500g未満)の割合は2倍以上、超低出生体重児(1000g未満)の割合は6倍になっている。通常の体重で生まれた子は粉ミルクで問題ないが、“ごく小さな赤ちゃん”の命を支えるのは母乳だ。何らかの理由で母の母乳を与えられないとき、助けになるのは他人の母乳を低温殺菌処理した「ドナーミルク」だが、供給は追いついていない。ドナーである母をはじめ、ドナーミルクを届けるため奮闘する人たちの思いや取り組みを探った。(取材・文:菅原さくら/編集:小山内彩希、Yahoo!ニュース オリジナル 特集編集部)
母乳提供は「今しかできない社会貢献」
「ドナーミルクを知ったのは妊娠中のこと。Instagramに流れてきた広告を見て、小さく生まれた赤ちゃんには母乳が必要で、寄付を募っていると知りました」と語るのは、子どもが生後3カ月を迎える頃から母乳を寄付している東京都在住のドナー・澤田未華さん(仮名)。
「『周りで不妊治療や早産の話を耳にすることも多いなか、私にもできることがあるのかもしれない』と思ったのが、ドナーになったきっかけです」
しかし、いざドナーになる方法を調べてみるとハードルが高く、産後に母乳育児が軌道に乗ってからもしばらくは悩んだ。
ハードルに感じたのは、「はじめに提携クリニックで検査を受けなければいけないこと」と、「自分の子どもが必要とする以上に母乳が出ること」という条件だった。
提携クリニックは全国的に少数で、東京23区内でも5施設のみ。澤田さんが行けるクリニックは予約枠が週1回で、赤ちゃんを育てながら予定を調整するのが難しかったという。
また、自分の子どもを完全母乳で育てていなければ、ドナー登録は認められない。海外では自分の子どもには授乳せずに母乳を販売し、生計を立てるケースもあるため、世界中の母乳バンクで“余剰分”のみをドナーから寄付していただくという厳格なルールが定められている。
それでも澤田さんは「母乳が出ている今しかできないこと。しかも、できる人が限られている社会貢献なのだから、やっぱり協力したい」と心を決め、少しずつ粉ミルクをやめて完全母乳に切り替えた。
[ad_2]
Source link