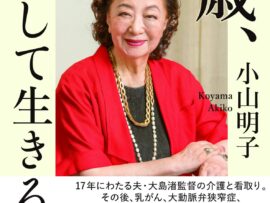厚生労働省は、2025年度の生活保護制度の監査方針の第一に「権利侵害の防止」を掲げた。不正受給対策を重視する姿勢からの転換。その背景には、「生活保護の利用者には、どのような非人道的行為をしても許される」と考える福祉事務所の出現や、「本人が言ってこないなら、役所は何もしなくても問題ない」とする申請主義のあり方が厳しく問われている現状がある。
重点事項は「権利侵害の防止」
生活保護の適用など運営面に関して、一部の実施機関における保護費の支給に関する不適切な取扱い、保護の相談・申請時及び廃止時の不適切な取扱い、職員による事務け怠等の不祥事や、稼働収入の無申告等による保護費の不正受給について報告を受けているところである。
このような事例の発生は、国民の生活保護制度に対する信頼を大きく損ない、ひいては制度の根幹を揺るがすことにもつながりかねない問題であり大変遺憾である。
(保護課自立推進・指導監査室「社会・援護局関係主管課長会議資料(令和7年3月)」) 25年3月12日、厚生労働省は、全国の担当者を集めた関係者会議で、生活保護制度における実施体制に強い危機感を示した。
具体例として示されたのは、「預貯金・現金の保有、ライフラインの記載がなく、相談者の急迫状況の確認を行っているか判断できない事例」、「保護申請には同居する世帯全員の同意が必要であると誤信させるおそれのある事例」、「本来保護申請に必要のない書類の提出を予め指示し、提出がなければ申請できないと誤信させるおそれのある事例」等々。
これらは、厚労省が禁止する「申請権の侵害、または申請権を侵害していると疑われる行為」、すなわち、権利侵害となる。
さらに厚労省は、「多数の実施期間において、複数年にわたり、同様の指摘が繰り返されており、効果的な監査が行われていない状況が認められた。これは、是正改善報告の審査及び実施方針等の策定についての指導が不十分であったことも一因であると考えられる」と続ける。
責任は、福祉事務所だけでなく、繰り返される権利侵害を止めようとしない都道府県や指定都市にもあるとしたのである。