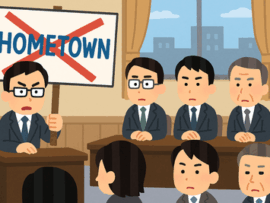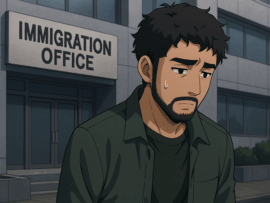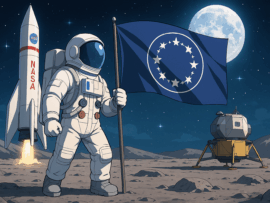[ad_1]
桜の時期の京都へ行ってきた。しかも週末だったから相当な混雑を覚悟していた。だが僕が訪れた場所はことごとく観光客がほとんどいなかった。あのオーバーツーリズム報道は何だったのか。
不思議に思いながら現地の人に聞くと、観光客はごく一部のエリアに集中しているのだという。具体的に言えば清水寺や祇園周辺。路線バスで言えば206系統沿い。確かに時間によって清水坂は満員電車のような混雑ぶりを見せる。
だが僕が好きな場所はどこも「過観光地」にはなっていなかったようだ。例えば太秦の広隆寺。足を組んだ弥勒菩薩半跏思惟像をはじめ、国宝や重要文化財の多い寺なのだが、ガラガラ。宝物庫も暗く案内も親切とはいえないので、あまり来場者を増やしたくないのかもしれない。空也上人像で有名な六波羅蜜寺も、清水寺に近いわりにそれほど人は多くない。誕生日で鑑定してもらう開運推命おみくじがあり、僕はよく友人へのお土産にしている。
他にも嵐山の大河内山荘、常寂光寺など見るべき場所は多い。足を延ばして鞍馬へ行くのもいい。今回、二条城はさすがに行列ができていたがオンラインでチケットを買えばすぐ入場できるし、アンゼルム・キーファー展(会期は6月22日まで)は空いていた。
うっかり本誌(「週刊新潮)」「とっておき私の京都」みたいなことを書いてしまった。言いたかったのは、京都のオーバーツーリズム解消に必要なのは、京都に観光客を入れないことではなく、むしろ京都各地を観光地化すべし、ということ。有名観光地に人が集まるのは必然だが、「有名」という指標は恣意的だ。高台寺はライトアップや呈茶体験などの企業努力ですっかり有名観光地になったが、数十年前は違った。「ねねの寺」として地元の人には親しまれていたが、境内は静かだったという。
イタリアのヴェネチアには世界中から観光客が押し寄せるが、歴史地区の人口5万人に対して年間訪問者は最大3000万人。京都市は人口140万人で観光客は5000万人。割合がまるで違う。ヴェネチアに比べればオーバーツーリズムでも何でもない。
ヴェネチアは2024年からは入島税を導入し、名実共に島全体が遊園地のようになった。僕が滞在した時も、至る所がインスタグラマーの撮影スタジオ化していた。
思想家の東浩紀さんは観光客を積極的に評価する。人口が減少する日本では移民にまつわる議論が飛び交うが、観光客にさえ拒否反応を示しているようでは本格的な移民受入などかなわない。まず観光で国際交流の「練習」をする必要があるのだ。もちろん全てを地元の善意に頼るべきではない。宿泊税はもっと高くしてもいいし、その分、街中のゴミ箱などのインフラを整備すべきだ。
未来の京都はどうなっているのだろう。地理的に京都は富士山噴火や津波などの自然災害の影響を受けにくい場所だ。いつかまた遷都があるかもしれない。
古市憲寿(ふるいち・のりとし)
1985(昭和60)年東京都生まれ。社会学者。慶應義塾大学SFC研究所上席所員。日本学術振興会「育志賞」受賞。若者の生態を的確に描出した『絶望の国の幸福な若者たち』で注目され、メディアでも活躍。他の著書に『誰の味方でもありません』『平成くん、さようなら』『絶対に挫折しない日本史』など。
「週刊新潮」2025年5月15日号 掲載
新潮社
[ad_2]
Source link