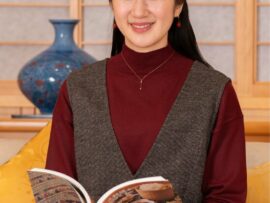全国の公立小・中学校には、通常学級(以下、通常級)のほかに“特別支援学級”(以下、支援級)が存在する。支援級では、発達障がいや情緒障がいなどを持つ子どもたちの自立を目指し、困難を改善・克服するために一人一人の状況に応じた指導を行なっている。このクラスで指導を受ける児童生徒は、2010年に約14.5万人だったが、2020年には約30.2万人まで増加し、その必要性はますます高まっている。しかし、今、一部の支援級は崩壊しつつあるという。その実態を取材した。
障がいを抱える子どもの特性を理解していない先生も
「4月初旬、支援級の新3年生になる息子の担任が発表され絶望しました。昨年度、通常級で学級崩壊したクラスを持っていたT先生だったからです」
そううなだれるのは、神奈川県内の公立小学校の支援級に通う息子を持つ保護者Yさんだ。「支援級」とは特別支援学級の略称で、小・中学校に設置されている障がいのある児童生徒を対象にした少人数の学級のことだ。
その発表があったのは、「T先生、支援級にきたらイヤだよね」と同学年の母親と話していた矢先のことだった。
「うちの学校の支援級は、通常級の担任が務まらなかった先生の“左遷先”のように扱われている節があります。『人数が少ないから大丈夫だろう』『言語障がい、発達障がいがあるから反抗してこないだろう』と安易に思うようです。
でも、実際は違います。支援級だと、自分を表現することが苦手な子や、こだわりの強い子などと向き合わないといけない。定型発達の子どもたちに満足に応対できなかった先生に、一人一人の特性を理解し、細やかな対応、授業進行ができるとは思えません。今後が不安でなりません…」(前出保護者・Yさん)
Yさんの学校に限った話ではない。取材を進めると、やる気をもって働く若手教師や保護者の信頼があるベテラン教師もいたが「前年度に学級崩壊」など問題を起こし、支援級の担任にされた先生の存在を複数確認できた。
千葉県内の公立小学校の支援級を卒業した女児を持つ保護者Hさんは、我が子の支援級を担当する先生には傾向があったという。
「娘がお世話になった小学校では、学級崩壊したクラスの先生のほかに、産休前後の先生、定年後の再雇用の先生などが担任をしてくれました。入れ替わりが激しく、担任が急に替わった年度もありました」(保護者・Hさん)
先生が急にいなくなることに、子どもたちは不安を感じるだろう。昨年、埼玉県内の公立小学校の支援級で「担任が急に替わり混乱した」と話してくれたのは、この小学校の新2年に通う女児の保護者Fさんだ。
「昨年6月、娘の担任だったK先生が急に辞めて、S先生に替わったんです。『体調不良で担任の継続が困難になった』と。K先生は、支援級の担当歴も長く、有資格(特別支援学校教諭免許状)者だったので安心していたのですが、やってきたS先生は免許がないどころか、支援級の担任は初めて。
S先生は、支援級に通う児童がどのような子どもたちなのかを一切理解しておらず、『一人一人の特性を理解したうえで指導をお願いしたい』と何度も伝えても、『一人だけ特別扱いはできない』と、通常級と同じように授業を進めようとしました」(保護者・Fさん)
文科省の『初めて通級による指導を担当する教師のためのガイド』 には、冒頭に「通級による指導は、子供の自立を目指し、障害による困難を改善・克服するため、一人一人の状況に応じた指導を行います」と明記されている。しかし、それさえも知らずに教壇に立っているという。
もちろん、真摯に仕事に取り組む、能力のある支援級の教師も数多くいるだろう。しかし、行政のシステムにも大きな問題があることが取材から分かってきた。