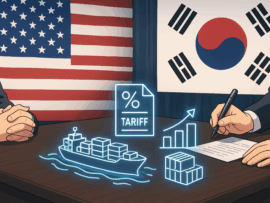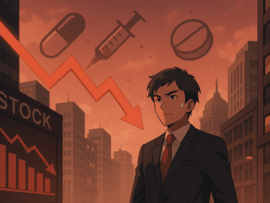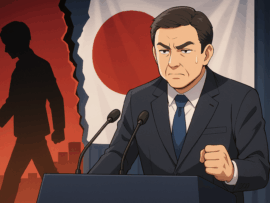[ad_1]
時代を変えた歴史人にはどのような特徴があるか。日本中世史の専門家である古野貢さんは「たとえば室町時代から戦国時代の扉を開けた細川政元には、制度疲労が起きている当時の常識を変えなければいけないという危機感があった」という――。
※本稿は、古野貢『オカルト武将・細川政元 室町を戦国に変えた「ポスト応仁の乱の覇者」』(朝日新書)の一部を再編集したものです。
■政元の魔法へのあこがれ
細川政元(ほそかわまさもと)には、男色(同性愛)に関係するエピソードが残っています。というのも、明応の政変後から、政元が内衆を殺す事件が起きてくるのですが、それを書き残した史料に「男色が云々」と批判的に書かれているのです。
もう少しあと、本格的な戦国時代に入ってきますと男色行為に対する見方も変わり、むしろ良いものであるというような印象が持たれるようになってきます。しかし、政元の時代では違っていたようです。
政元をめぐっては、史料に「飯綱の法など魔法を使うにあたっては女性と関わってはいけない、そうでないと魔法的な力がなくなってしまう」「だから四十歳までは妻帯しない」といった旨の記述が残っています。これらが政元の言動を強く規定している、とも考えられています。
彼が魔法などのオカルト的なものにハマっていった背景として、まず「空を飛びたい」などの具体的な願望は当然あるのでしょうが、加えて「人智を超えたものを大事にしたい、自分の基盤にしたい」という思いが根本的な行動原理としてあったのではないかと思われます。
■信念を貫くための呪術や修行
もう少し時代が下った戦国時代においても、合戦の前に占いをして勝利の可能性を高めようとしたり、上杉謙信が毘沙門(びしゃもん)天を信仰して勝利を神の加護によるものとしたりといった具合に、自分なりのよりどころを持ったものです。
政元の修験道への傾倒はその先駆けと言えるでしょう。しかし政元のそれは当時一般的だった仏教とか神道ではないものでしたから、日常生活の中においては「おかしなもの」であるという印象を与えたはずです。
しかし、政元からすれば筋の通ったことでした。
将軍との対立や自身が構想した政権を確立するという目標を設定した時、世間からどう見られようとも自分の信じるものを明確にしなければいけない、政元はそう考えたのではないでしょうか。
そこであらためて、政元が何を求めて呪術や天狗修行などのオカルトに辿り着いたのか、そしてその結果がどうなったのかを見てみましょう。
[ad_2]
Source link