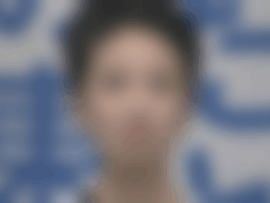[ad_1]
文部科学省が2024年10月31日に公表した「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」によれば、2023年度に不登校とされた小中学生は34万6482人となり、増加は11年連続、総数は過去最多で30万人を超えました。そうしたなかで、既存の学校にはない学びを追求するフリースクールやオルタナティブスクールといった学校が広がりつつあります。前屋毅さん著『学校が合わない子どもたち』(青春出版社)から、こうしたスクールが“普通の学校”と何が違うのか、抜粋して紹介します。
● テーマがバラバラ、でも目を奪われる子どもたちの掲示
「東京コミュニティスクール」(以下、TCS)は東京都中野区にあります。
小学生年齢の子どもたちを対象とする同校は、「認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)」が運営する学校です。創立から20年以上が過ぎており、不登校だった子もいれば、同校の居心地のよさに入学を決めた子なども通う、日本における“学校ではない学校”の先駆的存在のひとつでもあります。
初めてTCSを訪ねたのは2024年の夏休みが終わったばかりのころで、教室や階段の壁には、所狭しとたくさんの模造紙が貼られていました。一枚いちまいが子どもたちが夏休み中に取り組んだ個々の研究成果です。驚くのはテーマがバラバラなだけでなく、そのテーマも「スイカは果物か野菜か」などユニークなものばかりだったことです。
しかも、どれも本やパソコンなどで調べただけの、とおりいっぺんのものではありません。推論し、それを検証するためにインタビューまで行っている。スイカについても、スーパーの担当者に訊いた内容も盛りこまれていました。いわゆる「足で集めた情報」も満載で、かといって調べただけで終わりではなく、そこから考えていった報告者本人の結論もきちんと記されています。
公立小学校の授業参観(学校公開)に行くと、同じように子どもたちの作文や絵がたくさん貼りだしてある光景を目にします。ただし、そこにあるのは、「朝顔の観察日記」といった昔ながらの同じテーマのものばかりです。
子どもたちがまじめに取り組んだことは伝わってくるのですが、個性を感じるかといえば、まったく感じられないのが正直な感想です。そういうものと比べてしまうからかもしれませんが、TCSの掲示には見入ってしまって目が離せなくなったものです。
● “普通の学校”ではありえない授業風景
TCSの創立者は、久保一之(くぼかずゆき)さんといいます。彼にレポートのテーマのユニークさと内容の濃さを話したら、次の答えが返ってきました。
「ただインターネットや本で調べただけでは調査にならないとは、普段の授業でも言ってきていることです。ひとつの情報で結論を出すのではなく、複数の情報源をたどって妥当な結論を出すことをTCSでは大切にしています」
その授業も見学させてもらいました。決められた姿勢で行儀よく全員が椅子に座っているわけではなく、なかには立ち上がったり、席を離れたりする子もいます。だからといって、どの子も授業を無視しているのではなくて、テーマと正面から向き合っているのが表情からわかるし、発言もしています。向き合うときの形としての姿勢が違うだけです。
むしろ、「足をそろえて椅子に座り、きちんと前を向きなさい」などと指導していたら、テーマに向き合えないし、集中もできない子がいるかもしれません。手を挙げて当てられた子だけが発言する一方で、発言しないまま授業時間を終える子がいる“普通の学校”を想定していたら、ここでの風景は信じられないはずです。眉をひそめる昔気質(かたぎ)の人もいるかもしれません。そうした授業についても、久保さんに訊いてみました。
[ad_2]
Source link