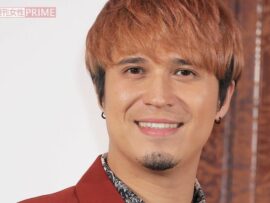中国政府は29日、2023年8月から続けていた日本産水産物の輸入禁止措置を約2年ぶりに一部解除した。29日から輸入が認められる地域がある一方、福島県など10都県に対する禁止措置は維持されたままだ。実際に水産物が中国に入るまでには1~2か月かかる見通し。
解除の範囲と条件
中国税関当局によると、今回の解除により、日本の水産業者が中国当局に輸出業者として再登録すれば、北海道や青森県など37道府県の水産物は登録日から中国向けに出荷を再開できる。処理水放出前と同様に、日本政府が発行する放射性物質検査などの証明書の提出が引き続き必要となる。
中国側の見解と今後の対応
中国外務省の毛寧(マオニン)報道局長は30日の記者会見で、今回の措置について「引き続き監督・管理を強化し、国民の食品安全を確保する」と説明した。さらに、「万一問題が発見された場合、必要な輸入制限を講じる」と述べ、今後の状況によっては再度制限を設ける可能性を示唆した。
解除の背景と日本側の反応
日中両政府が5月下旬に輸入再開に向けた手続きに合意した後、中国は1か月足らずで今回の輸入再開に踏み切った。トランプ米政権との貿易戦争を抱える習近平(シージンピン)政権には、アジア周辺国との関係改善を急ぐ思惑があるとみられる。小泉農相は30日、報道陣に対し「中国向け輸出が再開されることは大きな節目だ」と述べ、一定の評価を示した。しかし、中国側は過去2年余り、官製メディアなどで処理水の危険性を広くけん伝してきた経緯があり、福島県など10都県からの輸入再開には引き続き慎重な姿勢を崩していない。
 北京の日系スーパー、日本産水産物ではない旨の表示(禁輸措置の影響を示す)
北京の日系スーパー、日本産水産物ではない旨の表示(禁輸措置の影響を示す)
輸出回復の見通しと課題
中国による日本産水産物(缶詰や魚油を除く)の輸入額は、2022年の5億ドル(約720億円)から2024年には10万ドルへと激減し、事実上ゼロに近い状態だった。みずほリサーチ&テクノロジーズの月岡直樹氏は、今回の解除を受けても「一気呵成(かせい)に回復することにはならない」と指摘している。中国国内では節約志向が高まっており、日本産のブランド力と価格競争力の両面で、中国市場での支持を取り戻すための努力が必要となる。
結論
中国による日本産水産物禁輸措置の一部解除は、日本の水産業界にとって重要な一歩となる。しかし、福島県など10都県への措置が維持されている点や、過去の報道によるイメージ悪化、中国国内の経済状況といった課題が依然として残る。完全な回復には、市場での信頼と競争力を再構築するための継続的な取り組みが不可欠となるだろう。
※本記事は読売新聞の報道に基づいています。