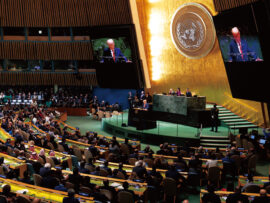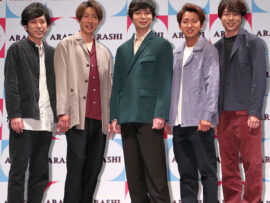昨年夏ごろから注目されている「令和の米騒動」は、発生から1年が経過しました。スーパーでの米平均価格は一時最高値を記録しましたが、直近の農林水産省の発表ではわずかに下落し、3ヶ月ぶりに3千円台に戻るなど、値下がりの傾向も見られます。
しかし、米の在庫が最も少なくなる夏を目前に控え、問題が根本的に解決されたわけではなく、課題は依然として山積しています。
 農林水産大臣の小泉進次郎氏。日本の米不足と価格高騰に関する政策決定者。
農林水産大臣の小泉進次郎氏。日本の米不足と価格高騰に関する政策決定者。
農林水産大臣が「備蓄米をじゃぶじゃぶ放出する」と発言したことなど、政府の対応に対しては、現場や専門家から疑問の声があがっています。元新聞記者として農業を取材し、現在は米・食味鑑定士やお米ライター、そして米農家の妻として活動する柏木智帆さんも、政府の施策には計画性が不足しているとの懸念を示しています。日本の米不足と価格高騰はなぜ発生し、その背景にはどのような構造的問題があるのでしょうか。
専門家が分析する米不足の要因
米農家の視点も持つ柏木さんは、今回の米不足と価格高騰が単一の原因ではなく、複数の要因が複合的に絡み合って発生したと分析しており、主に以下の5つのポイントを挙げています。
1. 栽培面積の持続的な減少:
過去10年間で、日本における米の栽培面積は約35万ヘクタールも減少しました。これは佐賀県の面積に匹敵する広さです。消費者の米離れが進む一方、それを考慮してもなお、生産基盤である作付け面積の減少幅は著しい状況です。
2. 小麦価格の上昇による米需要の増大:
天候不順やウクライナ情勢などの影響を受け、令和4年頃から小麦価格が高騰しました。これにより、比較的安価な米への代替需要が増加し、国内の米消費量が増える結果となりました。
3. 令和5年産米の高温被害:
昨夏の記録的な高温や乾燥により、米が白く濁る「乳白粒」が多く発生するなど、精米時の歩留まりが悪化しました。この高温被害を受けた米が多くなったことで、例年に比べて市場全体の流通量が減少しました。
4. コロナ禍を契機とした転作補助金の拡充:
コロナ禍で外食・中食産業における米の消費量が大幅に落ち込み、米余りが顕著になりました。これに対応するため、政府は米価下落を防ぐ目的で、主食用米から飼料用米や加工用米などへの転換を促す補助金を手厚くしました。結果として、主食米の生産量が意図せず抑制されることとなりました。
5. 昨年8月の災害情報による消費者心理:
昨年8月に発表された南海トラフ地震の臨時情報などを受け、多くの消費者の間で「いつもより多めに米を備蓄しておこう」という買い控えならぬ買い増し心理が働きました。これが結果的に、短期間における全体的な消費量を増加させました。
国の政策と現場の声
これらの要因の中でも、特に国の政策が現在の米不足に大きく影響していると柏木さんは指摘します。国は2018年に48年間続いた減反政策を廃止しましたが、その一方で飼料用米などへの転作補助金が拡充され、高い補助金を得られる転作を奨励することで、実質的な米の生産量調整は形を変えて続けられています。これにより、国内の主食米生産量が需要に対して不足しやすい構造が維持されていると言えます。インバウンド需要による米消費増も一部影響はありますが、根本的な問題は国内の生産・流通に関わる構造にあると考えられます。
また、都道府県ごとの米の出来具合を示す作況指数が、現場の実態と大きく乖離していることが以前から問題視されており、正確な需給バランスの見極めを困難にしていました。こうした状況に対し、農林水産大臣は今年6月に作況指数そのものを突然廃止すると発表しました。柏木さんは、作況指数に問題があることは事実としつつも、「いきなり廃止ではなく、米屋や卸など現場の声を丁寧に聞きながら、より良い需給予測のあり方を模索すべきだったのではないか。やや唐突で暴走気味な印象を受ける」と、その手法に疑問を呈しています。農家や米販売店など、現場の関係者はかなり前から減反や離農による米不足の可能性を懸念しており、今回の米騒動は「来るべくして来た」という見方が強いとのことです。
まとめ:構造的問題と今後の課題
日本の米価格は一時的ながらも最高値から下落傾向にありますが、専門家は今回の米不足と価格高騰が、栽培面積の減少、需要構造の変化、気候変動、そして国の政策や需給予測の不備といった構造的な問題に起因していると指摘しています。現場からの懸念は以前から存在しており、今回の騒動は単なる偶然ではなく、必然の結果として捉えられています。今後、日本国内での安定した米供給を維持していくためには、目先の価格変動に一喜一憂するだけでなく、生産現場や消費者の声を反映した、より実態に即した長期的な視点での政策立案と需給管理体制の構築が不可欠です。