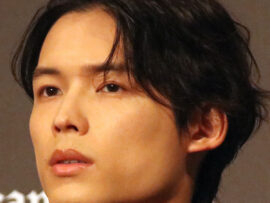2024年6月27日、最高裁判所は、2013年から2015年にかけて政府が行った生活保護基準の引き下げを「違法」とする画期的な判決を下しました。最高裁が政府の行為に対し明確に違法判断を示すことは極めて稀であり、これは政府による行いがどれほど重大であり、原告ら受給者の尊厳を深く傷つけるものであったかを強く示唆しています。生活保護制度は、事故、病気、失業、離婚、介護など、誰の身にも起こりうる不測の事態に備える、全ての人にとってのセーフティネットである社会保障の重要な柱です。その意味で、今回の政府の行為は、全ての国民に対する背信行為と言えます。しかしながら、この重大な判決に対する世間の反応は一様ではありません。SNSやニュースサイトのコメント欄には、「裁判をする元気があるなら働け」といった、政府の不正ではなく、むしろ困窮し裁判を起こした人々を誹謗中傷するような、的外れで非人道的な意見が少なくありません。
「不正受給」問題の現実と過剰なクローズアップ
そもそも、生活保護を本来必要としている人々のうち約8割が制度を利用できていない現状があるにもかかわらず、統計上、保護費総額のわずか0.5%未満(2023年度実績で保護費総額2兆7901億円に対し、不正受給額は97億3563.8万円)であり、悪質性の低いケースが多く含まれる「不正受給」が過度に注目を集めています。さらに、「私の知人が…」といった真偽不明の個人的な「不正受給事例」が事実であるかのように語られ、広まっていく傾向が見られます。
 厚生労働省の統計不正問題を連想させるイメージ
厚生労働省の統計不正問題を連想させるイメージ
この背景には、「生活保護」という言葉に対する「ずるい」「甘えている」「自業自得」といった根強い偏見と誤解が深く根差しています。このような偏見は、制度の正確な理解を妨げ、真に支援が必要な人々が萎縮し申請をためらう原因ともなっています。
「働きながら受給」は制度の理念に合致
ネット上ではいまだに「保護を受けているのに働いているのはズルい」といった声が見受けられますが、働きながら生活保護を受けることは、制度上全く問題ありません。むしろ、「できる範囲で働き、生活の一部を自らの力で支えること」は、生活保護制度が目指す自立支援の理念に合致する、推奨されるべき姿です。
また、「働いたら、稼いだ分は全部生活保護費から引かれるのだろう?」という誤解も根強いですが、実際には収入に応じて保護費が調整されるだけで、働いた分がそのまま差し引かれるわけではありません。「就労基礎控除」や「必要経費控除」といった控除制度が設けられており、働く意欲や努力が報われるよう、一定のインセンティブが存在します。
2023年度における生活保護の不正受給の内訳グラフ(厚生労働省データより)
これは、生活に困窮し一時的に「支えられる側」になったとしても、そこから再び自立へと歩みを進められるように設計されているからです。生活の困窮状況が変わらない限り、制度から締め出されることはありません。生活保護費は、生活を維持するための最低生活費に満たない不足分を補うものですので、就労による収入を適切に申告し、不足分を給付してもらうことは制度の趣旨に則った正当な行為です。
結論:正確な知識で偏見を払拭する重要性
最高裁判所による生活保護基準引き下げ違法判決は、政府の社会保障に対する姿勢の誤りを厳しく断罪するものでした。同時に、この判決が示した事実は、私たちが抱く生活保護制度への多くの誤解や根強い偏見を浮き彫りにしています。ごく一部の「不正受給」を過度に強調し、制度本来の目的や多くの受給者の努力を見過ごすことは、セーフティネットとしての機能を弱体化させ、真に困っている人々を孤立させることに繋がります。生活保護制度は誰にでも起こりうるリスクに対する備えであり、その正確な仕組みと現実を理解することこそが、不当な偏見を払拭し、制度がその役割を適切に果たせるようにするための第一歩と言えるでしょう。
参照文献
- 最高裁判所判決(2024年6月27日)
- 厚生労働省「全国厚生労働関係部局長会議資料(社会・援護局詳細版)」(令和6年度)