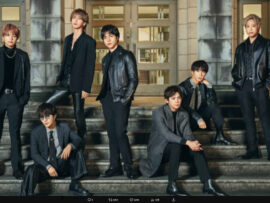2024年10月6日、ノーベル生理学・医学賞を受賞した大阪大学特任教授の坂口志文氏(74)。彼が30年前に発見した「制御性T細胞」は、自己免疫疾患の理解と治療に革命をもたらし、その功績は世界中で高く評価されています。しかし、この世界的偉業の裏には、厳格でありながらも国際色豊かな少年時代の教育環境が深く影響していたことが、親族の証言から明らかになっています。本記事では、坂口教授の類稀なる研究者としての道筋を、その生い立ちと家族との交流を通じて紐解きます。
 ノーベル賞受賞者の坂口志文大阪大学特任教授の肖像。彼が発見した制御性T細胞が自己免疫研究に大きく貢献した。
ノーベル賞受賞者の坂口志文大阪大学特任教授の肖像。彼が発見した制御性T細胞が自己免疫研究に大きく貢献した。
自己免疫研究のパイオニア:制御性T細胞の発見と未来へのメッセージ
坂口教授が受賞理由となった「制御性T細胞」の発見は、免疫システムが過剰に反応し、自身の体を攻撃してしまう自己免疫疾患のメカニズム解明に不可欠なものでした。彼の研究は、これらの疾患に対する新たな治療法の開発に繋がり、多くの患者に希望を与えています。ノーベル賞受賞会見で子どもたちへ向けたメッセージでは、「興味のあることを大切にする。それを続けることで新しいものが見えてきて、気が付いたら面白い境地に達する」と述べ、探究心と継続することの重要性を強調しました。これは、まさに彼自身の人生哲学を物語る珠玉のエールと言えるでしょう。
滋賀での厳格な教育:いとこが語る少年時代の学び
坂口教授の故郷は滋賀県長浜市。高校教諭の父・正司氏と、医師家系で同じく教育者であった母のもと、3兄弟の次男として生まれました。幼少期からの教育は非常に厳格で、いとこで医師の安井一清氏(73)は、そのスパルタ式教育を鮮明に記憶しています。安井氏によれば、坂口家ではテレビはNHKしか観ることが許されず、漫画を読むことさえも「もっと勉強しろ」と叱られるほど、徹底的に学業に集中するよう指導されたといいます。この環境が、後の坂口教授の学問への深い探求心と集中力を育む土台となったことは想像に難くありません。
知性と国際性の源流:父・正司氏とスカルノ大統領の知られざる交流
坂口教授の父、正司氏は京都帝大哲学科出身で、西洋哲学研究者を志していました。多言語に堪能なマルチリンガルであり、その国際的な感覚は、息子である坂口教授にも多大な影響を与えました。「シモン」という名も聖書にちなんで名付けられたものです。驚くべきは、父・正司氏が第二次世界大戦中、陸軍の連絡将校としてインドネシアに赴任していた際、後のインドネシア初代大統領であるスカルノ氏の世話をしていたという逸話です。当時、スカルノ氏は憲兵隊から目をつけられ身の危険もあったため、正司氏が約2カ月間保護していたと兄の偉作氏(76)は語ります。
この恩義を感じたスカルノ大統領は、1959年6月に日本を訪問した際、帝国ホテルで正司氏と再会を果たしました。同年6月17日付の朝日新聞夕刊には、「坂口元中尉と歓談 スカルノ大統領」という見出しで、その対面の様子が写真とともに報じられています。記事によれば、1942年3月にスマトラ島でオランダ軍が停戦し、自由の身となった大統領と正司氏が接触し、「占領初期につきものの誤解や行き違いのなかで同博士の世話をみた」とあります。このような国際的な背景を持つ家庭環境が、坂口教授の知的好奇心と視野の広さを育んだことでしょう。
難関を突破した京大医学部入学:逆境が育んだ弛まぬ努力
坂口教授は高校卒業後、1浪を経て京都大学医学部に入学しました。現役での受験時、学生運動の影響で東京大学の入試が中止となり、全国の秀才が京大に集中したため、不合格となったとされています。その後、予備校に通うのが困難であったため、自宅で自己管理しながら勉強に励む「宅浪」を選択しました。いとこの安井氏も、「浪人中は、自分で生活のリズムを作って勉強に励んでいました」と証言しており、この時期に培われた弛まぬ努力と信念を貫く姿勢が、後の大発見へと繋がる彼の研究者人生の礎となったことは間違いありません。
結論
坂口志文教授のノーベル生理学・医学賞受賞は、彼の卓越した知性と探求心の結晶ですが、その根底には、幼少期からの厳格な教育、父・正司氏の持つ国際性と知性、そして困難を乗り越えて京大医学部へ進学した際の弛まぬ努力がありました。滋賀県長浜市で培われた堅実な学びの姿勢と、家庭が育んだ広い視野が、世界的な研究者を形成する上で不可欠な要素であったと言えるでしょう。彼の功績は、自己免疫疾患に苦しむ人々への希望であると同時に、次世代の研究者たちへの力強いメッセージとなっています。
参考文献
- 週刊新潮 2025年10月23日号 掲載 (新潮社)
- 朝日新聞 夕刊 1959年6月17日付
- Yahoo!ニュース (記事元:新潮社) 2025年10月23日掲載