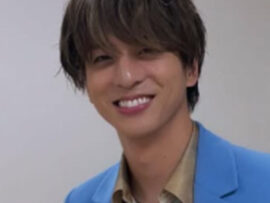職場で日常的に経験される、ハラスメントとまでは断定できないものの、相手に不快感や戸惑いを与える言動。これは「グレーゾーンハラスメント」と呼ばれ、日本の労働環境にじわりと影響を及ぼしている実態が、最新の調査で明らかになりました。「俺の若い頃は……」といった一方的な説教や、「あなたのためを思って」という名の不要なアドバイスなど、多くのビジネスパーソンがこうした言動に遭遇しています。東京都内の民間企業が行ったこの調査からは、グレーゾーンハラスメントが快適な職場環境をどのように侵害し、従業員の退職意向にまで影響を与えているかが浮かび上がっています。
調査で明らかになった職場の「不快な言動」
この実態を明らかにしたのは、社内規定DXサービスを提供する東京都港区のKiteRa社が2024年6月中旬に実施したインターネットアンケート調査です。全国の18歳から65歳までのビジネスパーソン1196人から回答を得ました。調査結果によると、業務上または日常の職場で、上司、部下、同僚からの「不快な言動」を経験したことがある人は全体の5割に達しました。具体的に経験された主な不快な言動(複数回答可)は以下の通りです。
- ため息や舌打ち、あいさつを返さないなど不機嫌な態度: 26.2%
- 社内の飲み会や接待への参加強制: 16.2%
- 過去の慣習や個人的な価値観・先入観に基づいた発言: 14.5%
- プライベートな質問に回答を強要: 12.0%
これらの項目は、明確なパワーハラスメントやセクシュアルハラスメントには当たらない場合が多い一方で、受け手にとっては大きなストレスとなり得るグレーゾーンの言動です。
 職場でのため息や舌打ちなど、グレーゾーンハラスメントを示すイメージ写真
職場でのため息や舌打ちなど、グレーゾーンハラスメントを示すイメージ写真
不快な言動が退職意向に与える深刻な影響
さらに調査は、これらの不快な言動が従業員の働く意欲や定着にどう影響しているかにも踏み込みました。不快な言動を経験した人のうち、「退職を検討したことがあるか」という問いに対して、45.8%が「はい」と回答しています。これは、グレーゾーンの言動であっても、無視できないほど従業員のエンゲージメントと定着に影響を与えていることを示しています。
個別の不快な言動がどの程度退職検討につながったかを見ると、最も割合が高かったのは「無視、仲間外れ」でした。この言動を経験した人のうち、7割が退職を検討していました。これは、全体の9.5%が経験した言動です。次に高かったのは「社外の飲み会や接待への参加強制」で、経験者の7割近くが退職を検討していました(全体の9.4%が経験)。これらの結果は、人間関係や心理的な疎外感が、たとえ直接的な業務命令でなくても、従業員の退職を強く促す要因となり得ることを示唆しています。
加害者の認識と社内規定の課題
興味深い点として、こうしたグレーゾーンハラスメントに当たる言動を「行ったことがある」と回答した人は全体の約4割にとどまりました。特にプライベートな質問をした経験がある人は15.3%、不機嫌な態度を取った経験がある人は11.4%でした。さらに、「行ったことがある」と答えた人の6割が、その言動を「良かれと思って」行ったという認識を持っていたことが明らかになりました。この結果は、ハラスメントの意図がなくても、コミュニケーションの取り方や態様によっては相手を不快にさせ、それがグレーゾーンハラスメントとなり得るという認識のギャップを示しています。
また、グレーゾーンハラスメントにあたる言動を抑制するための社内規定の有無についても調査されました。特に中小企業において、こうした規定の整備が遅れている実態が浮き彫りになっています。ハラスメントの法律問題に詳しい成蹊大学の原昌登教授(労働法)は、今回の調査結果について、「誰が見てもパワハラやセクハラに該当するのであれば、企業として対応すべきことは法律上明らか。しかし、グレーゾーン事案は対応が難しく、それゆえに注意が必要だ」と指摘しています。
まとめと今後の展望
今回の調査結果は、日本の職場で広く経験されている「グレーゾーンハラスメント」の実態と、それが従業員の不快感、ひいては退職意向に深く関連していることを明確に示しました。特に「無視、仲間外れ」や「社外の飲み会強制」といった人間関係に関わる言動が、深刻な影響を及ぼす可能性が高いことがわかりました。また、言動を行う側の「良かれと思って」という認識と、受け手の不快感との間にギャップが存在することも明らかになりました。
原教授は、立場を利用した言動により心理的負担を生じさせることを禁止するなど、的確で分かりやすい社内規定を整備することが有効であると提言しています。このような規定を通じて、従業員一人ひとりが自身の言動に注意を払うようになれば、お互いに不快感を与えず、世代間を含む円滑なコミュニケーションが可能になるでしょう。これは単にトラブルを防ぐだけでなく、企業にとってかけがえのない「財産」となり得るのです。グレーゾーンハラスメントへの適切な理解と対策は、今後の快適で生産的な職場環境を築く上で、避けては通れない課題と言えます。
参照元
https://news.yahoo.co.jp/articles/13b15ea84c2b254585465cdd284e10ecc0d5af95