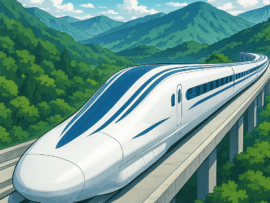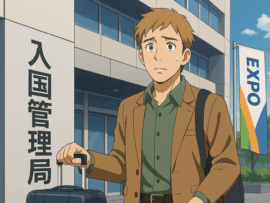福岡市博多区の自宅で、医療的ケアが必要な長女(当時7歳)の人工呼吸器を取り外して殺害したとして、殺人罪に問われた母親(45)の裁判員裁判の初公判が11日、福岡地裁(井野憲司裁判長)で開かれた。母親は罪状認否で起訴事実を「間違いありません」と認め、事件の背景にある深い孤独感や、夫・親族との関係性が明らかになった。検察側、弁護側双方の冒頭陳述では、母親がこれらの要因をきっかけに「無理心中を考えるようになった」と述べられ、事件に至るまでの経緯が語られた。
被告となった母親の背景と事件の概要
起訴状などによると、事件は今年1月5日午後に発生した。母親は自宅マンションのベッドにいた長女の首に挿入されていた人工呼吸器を自ら取り外して殺害したとされる。この痛ましい事件の中心にいる母親は、自身の娘に対し介護に専念する生活を送っていた。
長女は生まれつき、全身の筋力が進行性に低下する国の指定難病である「脊髄性筋萎縮(いしゅく)症(SMA)」を患っていた。自力での体動が不可能で、自発呼吸も困難な極めて重い状態であり、常に人工呼吸器やたんの吸引など、高度な医療的ケアが不可欠だった。
出生後は長期にわたり入院していたが、2歳10か月となった2019年末頃からは自宅での介護に移行した。夫との3人暮らしの中で、体の向きを変える介助やたんの吸引といった24時間体制の介護は、主に母親一人が担っていたという。2023年には仕事を辞め、利用できる福祉サービスも使いながら、娘の介護に全ての時間を費やす生活を送っていた。
 医療的ケア児殺害事件の初公判が開かれた福岡地裁
医療的ケア児殺害事件の初公判が開かれた福岡地裁
難病「SMA」と娘の壮絶な介護状況
検察側冒頭陳述では、長女のSMAが胎児期に発症する極めて稀なケースであり、弁護側からは「日本で一人だけの最重症患者だった」との説明もあった。これは、長女が一般的なSMAのケースと比べても、より手厚く、専門的なケアが絶えず必要であったことを示唆している。自宅での生活は文字通り、母親による24時間完全介護なしには成り立たない状況だった。
こうした中で、母親は精神的に追いつめられていった。検察側は、母親が親族から長女への音楽療法について「意味があるのか」と言われたことや、事件のわずか2日前に夫に介護の手伝いを頼んだ際に舌打ちをされ「寝れん」と言われたことなどを、無理心中を考えるようになった直接的なきっかけとして挙げた。これらの言葉や態度が、母親に「私と長女は要らない存在だ」という強い孤立感と疎外感を抱かせたとしている。
弁護側もまた、2014年からの不妊治療を経てようやく授かった待望の娘であったことを強調しつつ、夫の「寝れん」という言葉に対する怒りが癒えない中で、親族からの長女に向けられた無理解な言葉や態度を思い出し、深く傷ついたと述べた。弁護側は、これらの出来事が複合的に作用し、自身と長女が周囲に疎まれていると感じ、生きる場所がないという絶望感から心中を決意したと訴えた。事件当日、母親は人工呼吸器のアラームが鳴らないように設定した上で取り外し、自身も頭痛薬などを大量に服用して自殺を図ったが、後に病院に搬送され一命を取り留めたという。
裁判の焦点と社会への問い
裁判員裁判の初公判で母親が起訴内容を認めたことで、今後の審理では、彼女を犯行に駆り立てた動機、特に長期間にわたる壮絶な介護生活の中で積み重なった精神的負担や孤立、そして家族や社会からのサポート体制のあり方が重要な焦点となる。この事件は、医療的ケア児とその家族が直面する現実、介護疲れ、そして孤立という現代社会の課題を改めて浮き彫りにしている。判決がどのようなものになるか、そしてそこからどのような社会的な議論が生まれるのかが注目される。