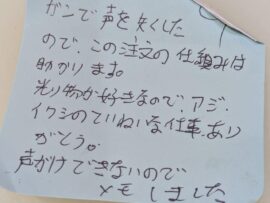神奈川県の中学受験国語塾「中学受験PREX」の渋田隆之塾長と、洗足学園中学高等学校の玉木大輔先生(校務主任・国語科)の対談後編をお届けする。2024年度、洗足学園は過去最高となる28名の東大合格者を輩出し、注目を集めている。この大学合格実績の背景にある、学力だけでなく生徒の視野を広げる独自の教育方針、特に「キャリア教育」について深く掘り下げる。
 洗足学園の玉木大輔先生と中学受験PREXの渋田隆之塾長が対談する様子
洗足学園の玉木大輔先生と中学受験PREXの渋田隆之塾長が対談する様子
大学合格実績に見る洗足学園の強み
洗足学園は2024年度入試で、東京大学に過去最高の28名が合格した。全生徒数約250名のうち、帰国生は約17〜18%、およそ40名程度だが、昨年度は帰国生のうち8名が東大に進学している。このような優れた合格実績は、特定の大学に特化した「東大コース」のような詰め込み教育によるものでは全くない。生徒たちは、中学から高校までの6年間を通して様々な経験をし、選択肢を最大限に広げた上で、高3になって初めて自身の進路を最終的に決定するのだという。
進路選択における「揺さぶり」教育の真意
洗足学園の教育の根幹にあるのは、生徒が中1の段階で進路を固定せず、たとえ特定の大学や職業を目指して入学してきたとしても、意図的に「揺さぶり」をかけ、「惑わせる」ことにある。これは、一度選択肢を広げ、多様な可能性を吟味する「奥行き」を持つことが、大学入学後やさらに社会に出てからの生徒たちの「伸び」につながると考えているためだ。では、具体的にどのような「揺さぶり」をかけるのだろうか。
志望を固めている生徒に対して、「その職業は素晴らしいけれど、他の職業を見なくて本当にいいのか」「本当にその大学でいいのか」と問いを投げかける。これは、生徒自身に「なぜそれを選んだのか」「他の選択肢にはどのような価値があるのか」を深く考えさせるためのアプローチだ。
高1での三者面談:健全な批判的議論の場
この「揺さぶり」教育の象徴的な場の一つが、高校1年生で行われる進路に関する三者面談だ。この面談では、生徒が保護者と教員を相手に、自身の考えうる進路についてプレゼンテーションを行う。理系に進みたいと表明した生徒に対しては、「なぜ行きたいのか」「その道のどういうところが良いと思っているのか」「文系ではだめなのか」など、保護者と教員が生徒のプレゼンに対し徹底的に深掘りし、問い詰める。これは、生徒の考えを単に追認するのではなく、健全な批判的議論を通じて、自身の選択に対する自信と納得感を育むための重要なプロセスだ。
多様な経験が育む自己決定力
このような進路選択における「揺さぶり」や深い議論を促す取り組みは、三者面談だけにとどまらない。洗足学園では、哲学対話、広範なキャリア教育プログラム、模擬国連への参加、学外コンクールへの挑戦といった「他流試合」を積極的に推奨している。生徒たちは、これらの多様な経験を通じて、自身の興味や適性、そして社会とのつながりについて多角的に考える機会を得る。
これらの経験と思索の積み重ねこそが、生徒が自身の進路について表面的な情報や他者の意見に流されることなく、自分自身で深く納得した上で最終的な選択を行う力、すなわち自己決定力を育むのである。
洗足学園の大学合格実績、特に東大合格者数の増加は、単なる受験対策に特化した教育ではなく、生徒一人ひとりの可能性を最大限に引き出す独自のキャリア教育の賜物と言える。多様な経験や健全な批判的議論を通じて、生徒は自身の進路について深く考え、納得のいく選択をする力を育む。この「揺さぶり」教育こそが、大学進学後や社会に出てからの「伸びしろ」につながる洗足学園の強みだろう。洗足学園の教育方針は、まさに次世代を担う人材育成の一つの理想形を示していると言えるだろう。
[参照元] https://news.yahoo.co.jp/articles/3d0c9db4d4adbd95c4a8e6e6f3f3d6cdafd82f21