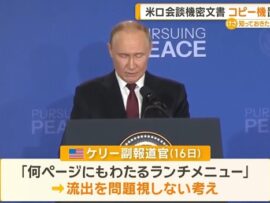大学生年代の扶養控除に関する重要な税制改正が、日本の国会で議論され決定されました。この改革により、大学に通う学生のアルバイト収入と、それを扶養する親の税負担の関係が大きく変わります。青山学院大学法学部教授である木山泰嗣氏は、令和7年の改正で、大学生の年間給与収入が150万円までは親の扶養控除が満額認められるようになった点を指摘し、教育現場で学生と接する立場からも、この改正は妥当であるとの見解を示しています。今回の改正は、特に「103万円の壁」問題の議論の中で早期に実施が決定されたもので、国民民主党の主張が反映されています。
扶養控除は、憲法の生存権保障を税制を通じて実現するための「生活費控除の原則」に基づくものです。子どもなどを扶養する親族には、自身とは別に最低生活費の負担が追加でかかるため、その部分の控除を認めるのが所得控除としての扶養控除です。扶養される人の年齢によって、所得控除の名称や金額は異なります。
大学生年代、具体的には19歳から22歳までの扶養親族を持つ場合、「特定扶養控除」として年間63万円の所得控除が認められます。これは、該当する大学生の子1人あたりの控除額であり、例えば大学生の子どもが2人いる家庭では、63万円×2人分として126万円が親の理論所得から控除されることになります。
しかし、令和7年の改正前は、この特定扶養控除を受けるためには、扶養親族である大学生自身の年間アルバイト収入を103万円以下に抑える必要がありました。もし学生の年間収入が103万円を超えると、親は特定扶養控除を受けることができなくなってしまうため、多くの大学生が自分のアルバイト収入が103万円を超えないように勤務時間を調整し、働くことを控えるという「103万円の壁」問題が生じていました。
 大学で学ぶ学生のイメージ(扶養控除に関連)
大学で学ぶ学生のイメージ(扶養控除に関連)
この問題は、単に学生がアルバイトで働く時間に制約がかかるだけでなく、アルバイトを雇う企業側にも深刻な影響を与えていました。特に年末などの繁忙期には、学生のアルバイト労働力が必要不可欠であるにもかかわらず、人手不足が発生してしまう状況が多々見られました。これは、税制が原因で経済活動に支障をきたす「困った税制」の一例とも言えるでしょう。
こうした「103万円の壁」問題が顕在化した背景には、近年継続的に上昇している最低賃金や、令和に入ってからの物価高といった経済状況の変化も大きく関係しています。以前よりも短い時間働くだけで103万円の壁に到達しやすくなったことが、問題をさらに加速させていたのです。

今回の令和7年税制改正により、大学生の年間アルバイト収入が150万円までであれば、親は引き続き特定扶養控除(63万円)を満額受けることができるようになりました。この変更により、大学生は税金の壁を気にすることなく、より多くの時間働くことが可能になります。これは、学生自身の収入増加につながるだけでなく、アルバイトを必要とする企業の人手不足解消にも貢献することが期待されています。専門家からも、現在の経済情勢や学生の状況を踏まえ、今回の改正は妥当な判断であると評価されています。
【参考資料】
木山泰嗣『ゼロからわかる日本の所得税制』(光文社新書)の一部再編集
Source link