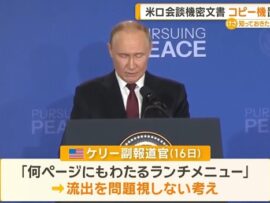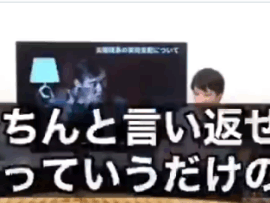壮絶な戦争体験を生き抜き、戦後の日本を築き上げた人々がいます。横山末雄氏(97歳)もその一人。海軍飛行予科練習生(予科練)としての過酷な経験を経て、札幌で全国有数のパン粉製造企業「横山食品」を設立しました。彼の原動力は、戦争で命を落とした仲間たちへの「報い」に他なりません。本記事では、横山氏の知られざる戦争体験と、それがどのように戦後復興へと繋がったのか、その軌跡を辿ります。
青春を奪われた時代:予科練への志願と過酷な訓練
横山末雄氏は現在の札幌市の農家に生まれ、1941年4月、札幌第一中学校(現・札幌南高校)に入学します。その8か月後、日本軍による米ハワイ・真珠湾攻撃で太平洋戦争が勃発しました。中学3年生の時、担任教師の勧めを受け、全国の若者が憧れる航空機パイロット育成課程、予科練の受験を決意し合格します。
母親の「何で志願してまで戦争に行くんだ」という必死の引き留めを振り切り、横山氏は茨城県の土浦海軍航空隊の門をくぐります。そこには想像を絶する容赦ないしごきが待っていました。教官による体罰は日常で、訓練の厳しさに耐えられたのは、故郷を離れる際に担任や同級生から贈られた寄せ書きのおかげです。その中央には、努力を知る担任が記した「地味な底力」という言葉。これが彼の心の支えでした。
 予科練入隊時に贈られた「地味な底力」の言葉が記された寄せ書き。過酷な訓練に耐える横山末雄氏を支えた精神的な支柱。
予科練入隊時に贈られた「地味な底力」の言葉が記された寄せ書き。過酷な訓練に耐える横山末雄氏を支えた精神的な支柱。
絶望的な戦況下での特攻志願と奇跡の生還
戦況は日を追うごとに絶望的なものへと向かいました。1945年5月、教官から「総員整列」の号令がかかり、「特攻隊を編成する。志願する者は一歩前へ!」との言葉が投げかけられます。「アメリカをやっつける」という強い思いに突き動かされ、横山氏は恐怖を感じることなく足を踏み出します。しかし、出撃の機会を得る間もなく、航空隊の拠点は壊滅的な打撃を受けました。
同年6月10日、空には米爆撃機「B29」約70機の編隊が現れ、「ゴーン、ゴーン」という不気味な飛行音が響き渡り、爆弾が雨のように降り注ぎます。横山氏は近くの防空壕へと駆け込み、両手で目と耳を塞ぎ、入り口から吹き込む爆風に必死で耐え抜き、九死に一生を得るという奇跡的な生還を果たしました。
戦後日本を支えた起業家精神:亡き友への誓いとパン粉の道
終戦後、横山氏は地元の北海道・札幌に戻り、荒廃した日本の復興期において「横山食品」を設立しました。彼が事業の柱として選んだのは、当時としては利益が少ないとされたパン粉製造でした。この堅実な選択の裏には、戦争で命を落とした予科練の仲間たちへの深い思いと、彼らの犠牲に報いようとする強い決意があったのです。
 札幌の工場でパン粉の原料となるパンを丁寧に確認する横山末雄氏。戦後復興を支えた堅実な経営姿勢を示す一枚。
札幌の工場でパン粉の原料となるパンを丁寧に確認する横山末雄氏。戦後復興を支えた堅実な経営姿勢を示す一枚。
横山氏は「地味な底力」という言葉を胸に刻み、一歩ずつ、堅実に会社を成長させていきました。過酷な予科練での訓練で培われた忍耐力と、故郷で培った勤勉さが、困難な道のりを乗り越える原動力となったのです。彼はただ企業を大きくするだけでなく、戦後の食文化を支え、日本経済の基盤を築く一助となりました。その事業は、亡き友への鎮魂歌であり、二度と悲劇を繰り返さないという平和への静かな誓いでもあったのです。
記憶を未来へ繋ぐ:横山末雄氏のメッセージ
横山末雄氏の人生は、壮絶な戦争体験と、そこから生まれた強い意志によって戦後の日本を築き上げた一人の実業家の物語です。彼の「仲間たちに報いる」という思いは、戦後日本の復興を支える精神的な柱となり、パン粉製造という地道な事業を通して、平和と繁栄への道を堅実に歩み続けました。
私たちは横山氏のような方々の証言を通して、戦争の悲惨さと平和の尊さを改めて認識することができます。彼の生き様は、困難な状況下でも希望を見出し、未来のために努力し続けることの重要性を私たちに教えてくれます。この記憶を風化させることなく、次の世代へと語り継いでいくことが、私たちの使命と言えるでしょう。