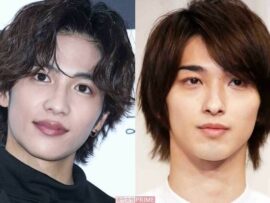大阪・関西万博での実証実験が一時中止されていた丸紅の「空飛ぶクルマ」HEXAのテスト飛行が再開されることが報じられました。今年4月のデモ飛行中に部品破損が発生し、その原因が設計仕様と異なる素材の部品が使用されていたことと判明したためです。その後、問題の部品を交換し、安全性が確認されたことで運航再開の目処が立ちました。今後は遠隔操作によるテスト飛行が続けられ、来たる7月12日にはデモ飛行が再び行われる予定です。「空飛ぶクルマ」に関するニュースが報じられるたび、特にSNSやニュースサイトのコメント欄では「これはクルマではない」「名称が不適切だ」といった名称論争が繰り返される傾向にあります。これらの反応は、空飛ぶクルマの社会実装に向けた重要な制度設計の議論を遅らせる一因となっている可能性があります。
大阪万博でのHEXAトラブルと繰り返される名称批判
丸紅による大阪万博での空飛ぶクルマHEXAの実証実験は、4月に発生した部品破損により一時中断されました。調査の結果、原因は本来の設計仕様と異なる素材の部品が使用されていたことと判明しました。問題の部品を交換し、安全性が確認されたことで、運航再開の運びとなりました。今後は遠隔操作によるテスト飛行を継続し、来たる7月12日にはデモ飛行が再び行われる予定です。
 名称論争の的となっている「空飛ぶクルマ」HEXAの機体イメージ
名称論争の的となっている「空飛ぶクルマ」HEXAの機体イメージ
しかし、こうした空飛ぶクルマの技術開発や実証実験の進展が報じられる一方で、論点とは異なる場所で批判が繰り返されています。それは「これはクルマではない」「名前が間違っている」といった名称論争です。この種の反応は、特にSNSやニュースサイトのコメント欄で頻繁に見られます。これらの意見は、必ずしも技術そのものへの深い理解を示すものではありません。むしろ、空飛ぶクルマを社会に受け入れるための制度設計という、より本質的な議論から目を背けるために現れている側面が強いと言えます。問題の核心は「クルマではない」という技術的な事実そのものではなく、名称の不正確さを過度に強調することで、制度設計の議論を先送りし、空飛ぶクルマの社会実装に伴う社会的責任や課題への関与を回避しようとする態度にあると考えられます。
技術分類の正確さよりも制度への組み込みやすさ
たしかに、現在の空飛ぶクルマ、すなわちeVTOL(電動垂直離着陸機)の技術的な仕組みは、従来の自動車工学における「クルマ」とは大きく異なります。車輪で道路を自走する機能はなく、外部からの操縦や電子制御によって飛行します。公道での車両登録や車検制度といった既存の枠組みは適用されません。そのため、技術的な観点から「クルマ」という名称が不正確であり、誤解を生むという指摘には、表面的な理屈はあります。
しかし、新しい技術やサービスが社会に導入される初期段階において、技術的な分類の厳密さが常に最優先されるべき課題とは限りません。「空飛ぶクルマ」という名称は、新しい制度設計を行う上で、一時的な、あるいは便宜的な呼び名として機能している側面があります。実際、政府の政策文書など公的な場でもこの言葉は使用されており、これは技術を既存または新規の制度の枠組みに組み込むための語として採用されていることを示唆しています。つまり、技術的に最も正確な分類よりも、社会実装に向けた制度への「入れやすさ」が重視されているのです。
名称への固執が制度議論を回避する言い訳に
それにもかかわらず、「これはクルマではない」という主張を繰り返し、その点に固執することは、空飛ぶクルマの社会実装に不可欠な制度設計に関わらないという態度の表れと見ることができます。こうした主張は、技術的な分類の差異を理由に、安全性、騒音、プライバシー、交通ルール、インフラ整備といった、より本質的な制度への参加や議論を回避するための言い訳にすぎません。
名称論争に終始することでは、空飛ぶクルマを安全かつ効果的に社会で運用するための制度が本当に正しいものになる保証はどこにもありません。必要なのは、技術の現実を踏まえつつ、どのようにして社会の仕組みの中に位置づけ、運用していくかという建設的な制度設計の議論なのです。
結論として、空飛ぶクルマに関する議論において、その名称の適切性のみに焦点を当てることは、社会実装に向けた喫緊の課題である制度設計の議論を遅らせる要因となり得ます。技術的な名称の正確さも重要ではありますが、それ以上に、この新しいモビリティを社会に安全かつ円滑に受け入れるための具体的なルール作りやインフラ整備といった制度面での議論を深めることが、今まさに求められています。