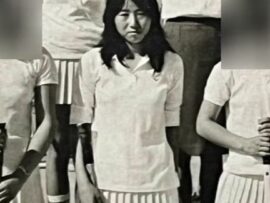私たちの日常生活に当たり前のように存在する「つまようじ」。その中でも、安心と品質を兼ね備えた国産つまようじが、今、深刻な危機に直面しています。河内長野市で半世紀以上にわたり、丸軸型の国産つまようじを製造し続けてきた菊水産業株式会社が、老朽化した機械のトラブルによる高い不良率に苦悩する現状をSNSで発信したところ、多くの共感と応援の声が寄せられました。長年培われてきた日本のものづくりを象徴する地場産業の存続に黄信号が灯る中、その背景にある課題と、私たちが国産品を守る意義について深く掘り下げます。
国産つまようじ製造の現状と機械トラブルの詳細
菊水産業が直面しているのは、製造の中核を担う機械の老朽化です。約50年前に導入されたこの機械は、北海道産の白樺原木から作られた約30cmの棒を、つまようじの標準的な長さである6cmに5等分する重要な工程を担っています。しかし、長年の使用により不具合が頻発し、不良品の発生率が著しく高まっています。このため、製造は続けられているものの、目視と手作業による検品の負担が膨大になり、廃棄量も増加。同社は厳しい経営状況に置かれています。菊水産業株式会社の末延秋恵社長は、「不良率が高くて辛い」と現状の苦しさを吐露しています。
修理・買い替えの困難と業界の特殊性
このような状況下で、機械の修理や買い替えは容易ではありません。末延社長によると、現在、丸軸型の国産つまようじを製造する企業は全国でわずか2社しかなく、かつて20社以上あった製造メーカーのほとんどが廃業しました。特に河内長野市では、菊水産業が地場産業として最後の1社となっています。つまようじ製造に特化した機械メーカーもすでに存在しないため、新品を導入するには数千万円規模のフルオーダーメイドが必須となります。単価の低い製品であるつまようじ製造において、これほどの巨額投資に踏み切るのは極めて困難です。
中国製の機械も市場には存在しますが、日本の規格との差異や、購入後のメンテナンス体制への不安が拭えません。日本の技術がかつて海外へ広まったにもかかわらず、今や機械を逆輸入しなければならないという複雑な思いも抱えています。わずかな希望として、現在1件の機械屋さんが現物を確認してくれることになっており、修理の可能性に期待が寄せられています。
 高品質な国産つまようじが積み重なっている様子。北海道産白樺の自然な風合いと、きめ細やかな質感が特徴の製品。日本のものづくりを象徴する一本一本が丁寧に作られています。
高品質な国産つまようじが積み重なっている様子。北海道産白樺の自然な風合いと、きめ細やかな質感が特徴の製品。日本のものづくりを象徴する一本一本が丁寧に作られています。
国産つまようじの類まれな魅力
では、なぜ国産つまようじを守る必要があるのでしょうか。その魅力は、高い品質と安心感にあります。菊水産業のつまようじは、北海道産の白樺原木を100%使用し、製造過程で薬品処理を一切行いません。これにより、自然素材そのものの安心感を消費者に提供しています。また、繊維が密に詰まっているため非常に丈夫で折れにくく、繊細な先端部分も潰れにくいのが特長です。実際に使用する顧客からは、「木の香りが心地いい」「口に入れるものだから国産の方が安心できる」といった高い評価が寄せられています。これらの声は、単なる日用品を超えた、国産つまようじが持つ独自の価値を物語っています。
地場産業を支える意義と菊水産業の挑戦
菊水産業が直面する課題は、つまようじ産業に限ったことではありません。機械の老朽化に加え、材料となる木材の確保の困難さ、環境問題への対応、人材不足、後継者問題など、多くの問題は国産材を使用する木工業全体に共通する悩みです。日本の地場産業を支える企業の多くは、家族経営の小規模な会社であり、「家族が食べていけたらいい」という素朴な思いで事業を続けてきました。しかし、昨今では高齢化とともに事業継続が難しくなり、廃業に追い込まれるケースが全国的に増加しています。
菊水産業もまた、小規模な会社でありながら、4年前にもらい火による火災で工場が全焼するという悲劇を経験しています。しかし、その時も多くの人々の支えによって再建を果たすことができました。この経験が、今回の機械トラブルという困難も乗り越えられるという強い信念につながっています。末延社長は、「これからは“夢のある仕事”にして、業界を発展させていくのが目標」と語ります。小さなものづくりであっても、そこに大きな価値を見出し、可能性を広げていくことこそが、日本の地場産業が未来へ進むための鍵となるでしょう。
社会からの支援と国産つまようじへの期待
菊水産業のSNS投稿は、瞬く間に多くの人々の心に響き渡りました。「ベテランの修理工が見つかりますように」「東大阪や尼崎あたりの町工場に修理できる人はいないのか」「国産つまようじを買って応援するしかない」など、具体的な支援策の提案や、国産製品への温かい応援の声が多数寄せられています。
この出来事は、私たちにとって身近な存在でありながら、その生産背景や価値について深く考える機会を与えてくれました。国産つまようじの存続は、単一製品の供給問題に留まらず、日本のものづくりの精神、そして地域経済を支える地場産業の未来に関わる重要な課題です。消費者として、国産つまようじの価値を再認識し、応援の気持ちを具体的な行動へと繋げていくことが、この大切な産業を守る一助となるでしょう。
参考文献
- まいどなニュース: 「なめらかで使い心地が良い国産つまようじ」機械トラブルにより、国産つまようじが危機に瀕している。 (2025年8月16日). https://news.yahoo.co.jp/articles/0abd698f5736458e1e418a6b43016785b32918a2