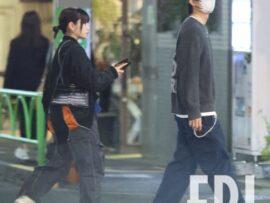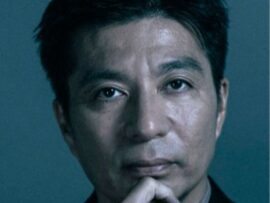中国北京市の裁判所は16日、アステラス製薬の日本人男性社員に対し、「スパイ活動を行った」として懲役3年6月の実刑判決を言い渡しました。中国当局は「国家安全」を盾に、反スパイ法の適用範囲を明確にしないまま不透明な運用を続けており、在留邦人の間では深刻な不安が広がっています。この判決は、一見和解姿勢を見せる日中関係の裏側にある、国家安全保障を巡る中国の強硬な姿勢を浮き彫りにしています。
中国「反スパイ法」運用の不透明性と在留邦人の懸念
今回の日本人社員への実刑判決は、中国の「反スパイ法」の運用における不透明性を改めて浮き彫りにしました。何がスパイ活動に該当するのかが明確に示されないまま拘束・起訴されるケースが相次いでおり、中国に滞在する日本人ビジネスパーソンや研究者の間で不安が募っています。
公判を傍聴した金杉憲治駐中国日本大使は16日、判決を受けて「邦人拘束事案は、日中間の人的往来や国民感情の改善を阻害する最大の要因の一つだ」と述べ、深い懸念を表明しました。この不透明な法の運用は、経済活動や学術交流に大きな支障をきたし、結果として中国に居住する日本人の減少にもつながっています。
 金杉憲治駐中国日本大使の肖像写真。大使は日中間の邦人拘束事案と反スパイ法の不透明な運用について懸念を表明している。
金杉憲治駐中国日本大使の肖像写真。大使は日中間の邦人拘束事案と反スパイ法の不透明な運用について懸念を表明している。
接近姿勢の裏に潜む「国家安全」の論理
北京の日系企業関係者からは、「なぜこの時期に判決公判が開かれたのか」と困惑の声が聞かれました。これは、中国政府が近年、日本に対し接近姿勢を示していると受け止められていたためです。実際、昨年11月には日本人への短期滞在ビザ(査証)免除措置が再開され、さらに日本産水産物や牛肉の対中輸出再開といった、これまで日中間の懸案となってきた問題の解消に向けた動きが進められていました。
このような中国の歩み寄りは、対中圧力を強める米国政権への対応に集中するため、周辺国との関係安定化を図る一環と見られています。経済や人の往来においては軟化姿勢を見せることで、国際社会における孤立を避けたいという思惑が背景にあると考えられます。
安全保障分野での強硬姿勢の継続
しかし、経済や人的交流における接近とは裏腹に、国家安全や安全保障に関する分野では、中国は一貫して強硬な姿勢を崩していません。今回の判決はその典型例と言えます。また、中国軍機が6月に続き、今月9日、10日にも自衛隊機に異常接近する事態が発生しました。これに対し、中国国防省は13日の報道官談話で、日本の行動が「中日間の海空安全保障上のリスクの根源だ」と一方的な対日批判を展開しています。
北京の外交筋は、現在の習近平指導部においては「国家安全や安保に関する政策の優先度が高く、外交とは異なる論理で動くようになっている」との見方を示しており、これが日中関係の複雑化を招く要因となっています。経済的な関係改善と国家安全保障上の強硬な姿勢という、二つの異なる顔を持つ中国政府の政策は、今後も日本にとって大きな課題であり続けるでしょう。
参考文献
- 産経新聞. (2025年7月16日). アステラス製薬社員に懲役3年6月 中国、不透明な反スパイ法運用に邦人不安. Yahoo!ニュース. https://news.yahoo.co.jp/articles/12ba36096e23619eadd434b91af1d8cfc1410860