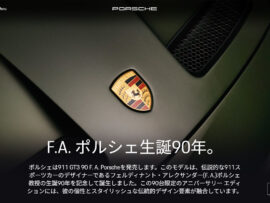言葉はビジネスの現場で重要な役割を果たします。特に時間の伝え方や指示の出し方は、受け手の解釈によって誤解を生みやすいデリケートな側面を持つため、注意が必要です。本記事では、新入社員とのコミュニケーションでよくある「時間の認識のズレ」をケーススタディとして取り上げ、お互いの理解を深め、より良い関係を築くための効果的な日本語コミュニケーション術をご紹介します。
ケーススタディ:新人との待ち合わせで生じた時間認識のズレ
ある日、あなたは新入社員と得意先を訪問することになりました。別件の都合で少し早めに現場へ向かう必要があったため、新入社員には「じゃあ、15時5分前に先方の会社の前で待ち合わせよう」と伝えました。ところが、約束の15時を過ぎてものんびりと現れた彼に「おい、遅刻だぞ!」と強く注意すると、キョトンとした顔で「えっ、まだ15時5分になってませんよ」と答えるではありませんか。
あなたは14時55分という本来の意図を伝えました。この状況で、あなたは新入社員に対して、どのように付け加えるべきでしょうか?
 職場で同僚と真剣に議論するビジネスパーソンたち
職場で同僚と真剣に議論するビジネスパーソンたち
「15時5分前」の意味、世代間のギャップとその危険性
多くのビジネスパーソンにとって、「15時5分前」は14時55分を指す「当たり前の常識」かもしれません。しかし、この言葉には意外な落とし穴があります。一部の人々、特に若い世代では、「15時5分」の「少し手前」と捉えてしまう可能性も否定できません。これは日本語の持つ曖昧さの一例であり、世代間の言葉の解釈におけるギャップが顕著に表れる場面です。
このような認識のズレは、単なる「遅刻」以上の問題を引き起こす可能性があります。業務の遅延、顧客への迷惑、そして何よりも上司と部下の間の信頼関係の構築を阻害しかねません。職場の円滑なコミュニケーションを保つためには、前提とする「常識」が必ずしも全員に共通するわけではない、という認識を持つことが重要です。
最善の対応策は?効果的なフィードバックの視点
では、先のケーススタディにおいて、どのような対応が最も適切でしょうか。選択肢として考えられる三つの対応について、その影響を検証します。
A案の問題点:感情的な指摘は逆効果
(A)「それにしても、ちょっと頭を使えばわかりそうなもんだけどな」
この発言は、相手を非難し、侮辱する響きがあります。新入社員は「頭が悪い」と攻撃されたと感じ、反発するか、あるいは萎縮してしまい、今後の業務で積極的に質問したり、報告したりすることを躊躇するようになるでしょう。「そうか、もっと頭を使わなきゃ」と建設的に反省するどころか、不信感ややる気の低下につながり、職場の生産性にも悪影響を及ぼしかねません。
B案の問題点:過度な自己責任は成長を阻害
(B)「今回は具体的な時間を言わなかった俺が悪かった。申し訳ない」
一見すると、上司が責任を認める謙虚な姿勢に見えます。しかし、この場合は新入社員に無駄に優位性を与え、彼らの成長機会を奪うことにもなりかねません。自分の解釈に誤りがあった可能性を顧みず、「上司が明確に伝えなかったから」という責任転嫁を許してしまうことになり、自己反省や確認の重要性を学ぶ機会を失わせてしまう恐れがあります。
C案の有効性:共感と相互確認で学びを促す
(C)「日本語は難しいねえ。次からはお互いに確認するようにしよう」
この対応は、最も建設的で、教育的なアプローチと言えます。まず「日本語は難しい」と共感を示すことで、新入社員の言い分を頭ごなしに否定せず、彼らの「なぜ?」という気持ちを理解しようとする姿勢を見せています。その上で「次からはお互いに確認するようにしよう」と提案することで、上司自身も伝達の責任の一部を担っていることを示しつつ、今後の行動指針として「相互確認」の重要性を明確に伝えています。
この言葉は、新入社員に「自分の常識が常に通用するとは限らない」という大切な気づきを与え、不明な点があれば自ら確認する習慣を促します。結果として、信頼関係を損なうことなく、より正確で円滑なコミュニケーションを促し、新入社員の自律的な成長を支援することにつながるでしょう。
結論
職場のコミュニケーションにおいては、言葉の持つ多義性や世代間の解釈の違いを認識し、前提や「常識」が常に共有されているわけではない、という意識を持つことが非常に重要です。特に新入社員への指示やフィードバックにおいては、感情的な指摘や過度な自己責任に陥ることなく、相手の状況に共感しつつ、明確な行動変容を促す言葉を選ぶことが求められます。
今回のケーススタディのように、「相互確認」の習慣を職場全体で育むことは、誤解を防ぎ、スムーズな業務遂行と円滑な人間関係を構築するために不可欠です。言葉の力を最大限に活かし、丁寧な対話を心がけることで、より生産的で信頼に満ちた職場環境を築きましょう。
参考文献
- 記事原案:石原壮一郎著「大人の言い換え力」より
- Source link: https://news.yahoo.co.jp/articles/46ae24fa1fe27d9836eaf92879c401cf54424c63