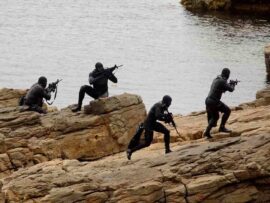多くの日本人が共有する行動原理の根底には、「周囲への配慮」が存在します。他人を不快にさせない、迷惑をかけない、そして相手を尊重するという考え方は、日常生活のあらゆる場面で優先され、「自分ファースト」よりも「他人ファースト」的な振る舞いにつながります。これは、個人の幸福を重んじる傾向が強い外国人から見れば、「Why Japanese people!」と驚かれるかもしれません。相手が特に気にしていないかもしれない事柄に対しても、先回りして思いやりを示すのが日本人特有の行動様式であり、これはオンライン空間にも色濃く反映されています。
現実世界に根差す日本人特有の「配慮」と行動
現実世界における日本人の行動様式は、しばしば他人への深い配慮に満ちています。例えば、エスカレーターでは片側を空け、エレベーターに乗れば率先してボタンを押す係になる。名刺交換ではお互いに順番を譲り合い、複数人で食事をする際、飲み物が先に届けば自分以外の相手にまず渡す、といった光景は日常的です。自分の飲み物が来るまでの間、気まずさを感じて「どうぞ乾杯してください」と促し、エア乾杯のような動作をすることさえあります。しかし、周囲も泡が消えることを気遣い、なかなか口をつけない、といった独特のやり取りが生まれるのです。
この「他人ファースト」の精神は、特にビジネスメールのやり取りにおいて顕著に表れます。日本のビジネスメールは、「(相手の苗字)様」「いつもお世話になっております」といった丁寧な導入から始まり、本題に入るまでに長い前置きがあるのが一般的です。一方で、アメリカなどでは「あなたにギャラ減額をしてもらう件で今回はメールを書いています」と、いきなり結論を切り出すことも珍しくありません。締めくくりの言葉も、日本では「暑さの厳しいおり、くれぐれも体調を崩さぬようご自愛ください」といった相手を気遣う文言が用いられるのに対し、海外では「〇月〇日までに返事をするように」と簡潔に指示されるケースも少なくありません。
このような丁寧な対応は、実際に知り合いや仕事上の関係者に対してであれば理解できますが、多くの日本人は、ネット上の見知らぬ他者に対しても同様の配慮を示す傾向があります。インターネットが一般化してから30年近くが経ちますが、その黎明期から現代に至るまで、日本人らしいオンラインでの振る舞いは数多く見受けられます。
 スマートフォンを操作する手元と、多様なSNSアプリのアイコンが表示された画面。各SNSに存在する日本人らしいネットルールやオンラインマナーの多様性を示唆する画像。
スマートフォンを操作する手元と、多様なSNSアプリのアイコンが表示された画面。各SNSに存在する日本人らしいネットルールやオンラインマナーの多様性を示唆する画像。
ネット黎明期から現代へ:独特のオンラインマナーの進化
ネットが普及し始めた頃から、日本のオンラインコミュニティでは独自の「暗黙のルール」や「ネットマナー」が形成されてきました。これらは現実社会の「空気読み」や「配慮」の精神が、デジタル空間に持ち込まれた結果と言えるでしょう。
mixiの「足あと」と「踏み逃げ禁止」文化
かつて主流だったSNSの一つ、mixiでは、「足あと」というユニークな機能がありました。これは、自分のプロフィールや投稿を見たユーザーの履歴が残るというもので、多くのユーザーはこれを活用していました。しかし、中には自身の投稿を閲覧したにもかかわらず、何もコメントを残さない行為を「踏み逃げ」や「読み逃げ」とみなし、これを禁止するユーザーも存在しました。つまり、「私のページを訪れたのだから、何らかの感想や挨拶を残すのがマナーではないか?」という期待があったのです。そのため、「踏み逃げ禁止」を掲げるユーザーに対しては、「とても楽しそうですね(*^ω^*)」のような短い、当たり障りのないコメントを残すことが一種のマナーとして認識されていました。
2ちゃんねるに学ぶ「半年ROMれ」の流儀
匿名掲示板2ちゃんねる(現在の5ちゃんねる)には、「半年ROMれ」という有名な用語があります。これは、長年続く常連ユーザーが集うスレッドに新参者が参加した際に、その場の雰囲気やルール、独特の言葉遣いを理解せずに発言した場合に浴びせられる言葉です。例えば、「今北産業」や「バカのすくつ」といった独特のインターネットスラングに対し、「それはどういう意味ですか?」と尋ねたり、「『すくつ』ではなく『そうくつ』です。ほら、巣窟と出るでしょ?」などと指摘したりすると、「半年ROMれ」という攻撃的な反応が返ってきました。これは、「少なくとも半年間はRead Only Member(読み取り専用メンバー)として、一切書き込みをせずに2ちゃんねるの作法や文化を学ぶべきだ」という意味合いで使われました。この文化は、ラーメン二郎の初心者に対して常連客が示す「暗黙のルール」や「空気感」にも通じるものがあります。
GREEに垣間見た「完全無欠」な他己紹介の世界
現在ではソーシャルゲームプラットフォームとして知られるGREEですが、その初期には意識の高い若手ビジネスマン向けの交流SNSとしての側面も持っていました。そこには「自己紹介」ならぬ「他己紹介」という、友人を他者に紹介する機能が存在しました。この機能は、紹介文が美辞麗句に溢れ、しばしば「歯の浮くような」表現が用いられることで知られていました。例えば、「山田さんは僕の人生の節目節目で適切なアドバイスをくださった“アニキ”です。就職、部署異動、転職など都度相談に行き、常に僕の背中を押してくれました。頼れるアニキ! これからもよろしくお願いします!」といった調子です。このように、誰もが完璧で非の打ちどころのない人物として紹介される光景は、当時のGREEならではの圧巻の文化でした。
日本のオンライン行動が映し出す「気遣い」の哲学
現実世界で培われた「他人への配慮」や「空気を読む」という日本独自の文化は、インターネット空間にも自然と浸透し、mixiの「踏み逃げ禁止」、2ちゃんねるの「半年ROMれ」、GREEの「他己紹介」といった独特のオンラインマナーを形成してきました。これらの慣習は、時に閉鎖的、あるいは過剰な配慮と受け取られることもありますが、その根底には「皆が気持ちよく過ごせるように」という共通の願望があります。オンラインのコミュニケーションツールが多様化し、文化も変化していく現代においても、日本人特有の「気遣い」の哲学は、見えないルールとして私たちのデジタルライフに深く息づいていると言えるでしょう。