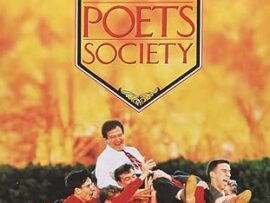国土交通省 九州運輸局は2025年7月10日、管内で実施した特別街頭検査の結果を公表しました。この検査により、不正改造車8台に「整備命令書」が交付され、そのうち7台が二輪車だったと報告されています。公道の安全と秩序を脅かす不正改造車両に対し、当局が厳格な姿勢で臨んでいることが浮き彫りになりました。
不正改造車とは? 定義と危険性
公道を走行する全ての車両は、安全と環境に関する基準を定めた「保安基準(道路運送車両の保安基準)」に適合している必要があります。不正改造車とは、この保安基準に適合しないように装置を取り付けたり、取り外したり、あるいは改造を施した車両を指します。このような状態で公道を走行することは違法であり、他の交通参加者に重大な危険や多大な迷惑を及ぼす可能性があります。
具体的な不正改造の例として、消音器(マフラー)の取り外しや保安基準に適合しない製品の装着が挙げられます。これにより、車両の走行時だけでなく、エンジンの始動時やアイドリング時にも近隣に爆音が響き渡り、騒音公害となります。また、運転中に爆音のためにクラクションや緊急車両のサイレンが聞こえにくくなり、事故のリスクが高まります。
車高を極端に低くする「シャコタン(車高短)」と呼ばれる改造も危険です。保安基準で定められた最低地上高9cmを下回る場合、車体やマフラー、エンジン下部などを路面にぶつけ、車両が走行不能となり、渋滞を引き起こす可能性があります。さらに、道路鋲やマンホールといった設備を破壊したり、車体と路面の接触による火花の発生で火災に至る危険性も秘めています。
車体幅を超えるウイングやスポイラーなども、取り付けが不十分であれば走行中に脱落し、後続車や歩行者に重大な傷害を与える恐れがあります。その他、ライトの色や光り方の変更、着色フィルム(スモークフィルム)の貼付、タイヤを車体からはみ出させて回転部分を露出させる行為、トラックの速度リミッター解除なども、保安基準適用外の不正改造に該当します。
不正改造車愛好グループの実態と社会への影響
不正改造は単なる個人の嗜好に留まらず、不正改造車を愛好する者たちが集団を形成しているケースも少なくありません。「暴走族」(珍走団とも呼ばれる)や「旧車會」、「ドリフト族」、「走り屋」、「ルーレット族」、「環状族」といったグループがその典型です。
これらの集団は、不正改造車での爆音走行や迷惑行為に加えて、高速道路のサービスエリアやパーキングエリア、道の駅などに集結し、空ぶかしやドリフトなどを行い、近隣住民や一般のドライバーに多大な迷惑と不安を与えています。
 九州運輸局による不正改造車の特別街頭検査の様子。検査官が車両の改造状況を確認している場面。
九州運輸局による不正改造車の特別街頭検査の様子。検査官が車両の改造状況を確認している場面。
国土交通省の取り組みと九州運輸局の最新報告
国土交通省は毎年6月を「不正改造車の強化取り締まり月間」と定め、全国各地で警察、運輸支局、自動車技術総合機構などの関係機関と連携し、特別街頭検査(検問)を積極的に実施しています。
今回、国土交通省 九州運輸局は九州管内の各地域で強化取り締まりを実施し、合計556台の車両を検査しました。その結果、8台の車両において保安基準不適合または整備不良の箇所が確認され、その場で検挙されました。特に注目すべきは、検挙された8台のうち7台が二輪車であった点です。
検挙された車両の使用者には「整備命令書」が交付されます。この命令書は、交付から15日以内に車両を保安基準に適合するよう修理し、最寄りの陸運局などで検査を受けなければならないという義務を課すものです。九州運輸局は、「強化月間のみならず、関係機関と協力し、街頭検査を実施することとし、不正改造車の排除に努めるとともに自動車の使用者に対し指導等を行ってまいります」と表明し、“排除”という強い言葉で不正改造の撲滅を目指す断固たる姿勢を示しています。
昨年度の取り締まり実績と無車検車両への対応
九州地方では依然として多くの不正改造車が確認されており、昨年度(2024年度)は176回という頻繁な街頭検査が実施され、徹底した取り締まりが行われました。
昨年度の一連の街頭検査では、延べ1万3367台の車両がチェックされ、そのうち85台の不正改造車が検挙され、その場で整備命令書が交付されています。主な不正改造の内容としては、マフラーの取り外し、着色フィルム(フルスモーク)の貼付、最低地上高の不足(シャコタン)が中心でした。
また、無車検の車両に対する取り締まりも強化されており、ナンバープレートの自動読み取り装置を活用した街頭検査では、昨年度に20回実施され、合計2万2625台がチェックされました。このうち23台の無車検車両がその場で検挙されるに至っています。
まとめ
国土交通省 九州運輸局による不正改造車への厳格な取り締まりは、公道の安全確保と交通秩序の維持に不可欠です。特に二輪車における不正改造が多数確認された今回の結果は、特定の車種に対する意識啓発と取り締まりの重要性を改めて示しています。車両の所有者は、自らの安全だけでなく、他者への影響を考慮し、常に保安基準に適合した状態で車両を運転する責任があります。今後も、不正改造車の排除に向けた継続的な取り組みが期待されます。
参考文献:
- くるまのニュース編集部 (2025年7月24日). 不正改造車8台のうち7台が二輪車. Yahoo!ニュース. https://news.yahoo.co.jp/articles/c857034c634d8a83449402a7e962ad800df47dd8