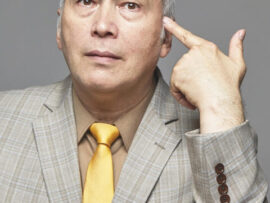近年、高齢者が持ち家を売却し、賃貸住宅へ移り住むケースが増加しています。例えば、70歳の母親が1500万円で自宅を売却後、月15万円の家賃生活に苦悩するといった事例は、多くの家庭で直面する可能性のある現実です。まとまった現金が得られる一方で、その後の家賃負担が年金収入を圧迫し、生活が厳しくなることも少なくありません。本記事では、高齢者が持ち家を手放す際に考慮すべき影響、住み慣れた家に住み続ける方法、そして賃貸生活に移行する際の重要な障壁と対策について詳しく解説します。
持ち家売却が老後の生活に与える影響とは
高齢者が自宅を売却して現金を確保する選択は、確かに資産の流動性を高めるというメリットがあります。特に、リフォーム費用、介護費用、あるいは施設入居費用に備える目的で選ばれることが多く、所有に伴う維持コストや固定資産税、修繕費といった負担からも解放されます。
しかし、その一方で、新たに賃貸住宅に移ると、月々の家賃支払いが生活費に大きな影響を与えます。仮に家賃が月15万円であれば、年間で180万円もの支出が発生します。1500万円の売却資金があったとしても、このペースでは約8年ほどで尽きてしまう計算です。年金収入だけでは賄いきれない場合が多く、貯金の取り崩しが前提の生活になりがちです。このような状況を避けるためには、自宅売却前に、老後の長期的な住居費をシミュレーションし、詳細なキャッシュフローを把握しておくことが不可欠です。
 高齢者の持ち家売却と老後の住居費問題について考える様子を示す画像
高齢者の持ち家売却と老後の住居費問題について考える様子を示す画像
住み慣れた自宅に住み続ける「リースバック」という選択肢
持ち家を売却しても、引っ越しをせず同じ場所に住み続ける方法として、「リースバック」という仕組みがあります。これは、自宅を第三者(リースバック事業者など)に売却し、その買主と賃貸契約を結ぶことで、元の自宅にそのまま住み続けることができるサービスです。
リースバックの主な特徴は以下の通りです。
- 自宅を売却してまとまった資金を確保できるため、老後資金や医療費などに充てられます。
- 引っ越しをする必要がなく、住み慣れた生活環境や人間関係を維持できます。
- 所有権が買主に移転するため、固定資産税や都市計画税、将来的な修繕費用などの所有者負担から解放されます。
ただし、リースバックには留意すべき点もあります。家賃は買主の意向により決定されるため、相場より高額になる可能性も考えられます。また、賃貸契約である以上、契約更新の拒否や家賃の引き上げリスクも存在します。長期的な居住安定を希望する場合は、契約内容(家賃設定、契約期間、更新条件など)を事前に、かつ慎重に確認することが極めて重要です。
高齢者が新規賃貸契約を結ぶ際の課題
高齢者が新たに賃貸住宅を借りる際には、さまざまな制約や障壁が存在します。特に70歳以上の単身者や高齢者夫婦の場合、以下のような問題に直面しやすくなります。
- 入居審査の厳しさ: 貸主は、高齢の入居者に対して、孤独死のリスクや家賃滞納のリスクを懸念する傾向があります。そのため、若い世代に比べて入居審査が厳しくなることが多く、希望する物件が見つかりにくい場合があります。
- 保証人の確保が必要: 親族に頼れる保証人がいない場合、家賃保証会社との契約が必要となることがほとんどです。これにより、敷金・礼金などの初期費用に加えて保証料が発生し、経済的な負担が増える可能性があります。
- バリアフリーでない物件が多い: 既存の賃貸物件の中には、高齢者に適した間取りや手すりの設置、段差の解消といったバリアフリー設備が整っていないケースが少なくありません。身体機能が低下しても安心して暮らせる物件は限られているのが現状です。
これらの課題を乗り越えるためには、「高齢者向け住宅」や「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」など、高齢者の受け入れ体制が整っている特定の選択肢を検討することが重要です。これらの施設は、安否確認や生活相談サービスが提供される場合もあり、安心して暮らせる環境が期待できます。
自宅売却後の老後の住まいを考える際には、安易な判断は避け、リースバックの利点とリスク、そして新たな賃貸生活における障壁を深く理解することが不可欠です。長期的な視点での住居費シミュレーションと、専門家への相談を通じて、ご自身やご家族にとって最適な選択を見つけることが求められます。