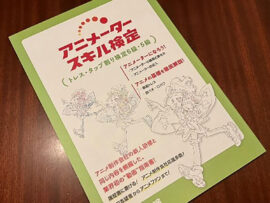「なぜ、そう思うの?」といった「なぜ?」と問う質問は、一般的に論理的思考を促す「良い質問」だと考えられがちです。しかし、実はこの「なぜ?」という問いかけは、致命的な「解釈のズレ」を生み出し、会話の「空中戦」を招く元凶となり得る「最悪の質問」であると指摘されています。事実と解釈の違いを理解せずに行われる対話は、まさに“曇りガラス”越しのようなもので、真意が伝わりません。世界各地で実践と観察を重ねてきた対話のプロが辿り着いた「なぜ」と聞かない質問術、すなわち「事実質問術」が、話題の新刊『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』で紹介されています。本稿では、その衝撃的な内容の中から、特に避けるべきNG質問について深く掘り下げます。
「なぜ?」が引き起こす「解釈のズレ」と「空中戦」
「なぜ?」という問いかけは、一見すると相手の思考を深掘りし、問題の本質に迫るための有効な手段のように思えます。しかし、この質問がしばしば「解釈のズレ」を引き起こし、建設的な対話を妨げる原因となることがあります。人は「なぜ?」と問われると、自身の行動や考えを「正当化」しようとする心理が働きがちです。特に、過去の出来事に対してその理由を問われた場合、相手は無意識のうちに自分を守るための説明、すなわち「言い訳」を探し始める傾向があります。この状況下では、事実に基づいた客観的な対答ではなく、自己の解釈や感情が混じった主観的な説明になりやすく、結果として話が噛み合わない「空中戦」に陥りがちです。この問題は、ビジネスの現場だけでなく、日常生活における親しい間柄、特に親子の対話においても顕著に現れます。
 「なぜ」という質問が親子の会話に引き起こす誤解。効果的な対話術の重要性を示唆。
「なぜ」という質問が親子の会話に引き起こす誤解。効果的な対話術の重要性を示唆。
子育てにおける「なぜ」の危険性:詰問と信頼関係の破壊
子育ての場面で、「どうして言うことが聞けないの!」「なんでこんなことしたの!」と子どもに問い詰めてしまうことは、多くの親が経験することかもしれません。しかし、このような「なぜ?」を使った質問は、子どもにとって強い「圧」となり、心にネガティブな経験として刻まれてしまいます。例えば、親が「なんでゲームまだ片付けてないの?」と問うと、子どもは「さっき片付けようと思ってたけど、トイレ行きたくなって…」と、つい自分を守るための「言い訳」をしてしまうことがあります。
親は「しっかりした子に育ってほしい」という親心から質問しているのですが、このような問いかけは、実は「質問のふりをした詰問」に他なりません。既に起きてしまった過去の行動や失敗の原因を問い詰めることは、相手に弁解の余地を与えず、心理的に追い詰めることになります。これは子どもに限らず、大人同士のコミュニケーションでも同様です。詰問された側は、自己防衛のために嘘をついたり、事実を歪曲したりする可能性も出てきます。結果として、親子の間にあるべき信頼関係が深まるどころか、むしろ損なわれていくことに繋がりかねません。
より良い人間関係を築く「事実質問術」への道
人間関係の基本は良好なコミュニケーションにあり、その出発点には「良い質問」が存在します。従来の「なぜ?」という問いかけが、対話のズレや信頼関係の毀損を招く危険性を孕んでいるとすれば、私たちは質問の仕方を見直す必要があります。本書が提唱する「事実質問術」は、相手の解釈や感情に焦点を当てるのではなく、客観的な事実に基づいた問いかけをすることで、真の状況理解と建設的な解決策へと導きます。この「なぜ」と聞かない質問術を習得することは、親子関係だけでなく、あらゆる人間関係においてより深い信頼と円滑なコミュニケーションを築くための鍵となるでしょう。
参考文献:
- 中田豊一 著『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』ダイヤモンド社 (2025年7月30日発売)