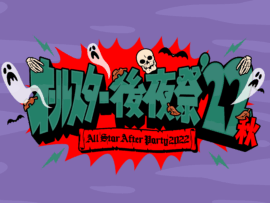日本語が外国人にとってなぜ「不思議な言語」と映るのか。日本在住25年の応用言語学者、アン・クレシーニ氏(北九州市立大学准教授)は、その理由の一つに「二重否定」を挙げます。「歩いていけなくもない」といった表現は、日本語学習者をしばしば困惑させます。本記事では、この日本語特有の「二重否定」の複雑なニュアンスと、その奥深さを解説します。
日本語の「二重否定」が外国人学習者を悩ませる理由
日本語の表現の中でも、外国人にとって特に理解が難しいのが「二重否定」です。日本人には無意識に使う表現ですが、その意味は奥深く、曖昧に感じられます。「現金しか使えません」「わからなくはない」「駅まで歩いて行けなくはない」といった表現は、二つの否定語で肯定を弱めたり、複雑なニュアンスを加えたりします。
外国人からは、「『駅まで歩いて行けなくはない』と言われると、本当に歩けるのか、無理なのか明確な答えが得られず困惑する」という声が聞かれます。この「どっちつかず」な表現が、日本語の難しさであり、同時に豊かな表現力を生む側面でもあります。日本語の二重否定は、話し手の婉曲的な意図や、相手への配慮を示す際に用いられることが多く、直接的な表現を避ける文化的な背景とも関連しています。
 日本語学習に悩む外国人女性。複雑な日本語の二重否定表現に困惑する様子。
日本語学習に悩む外国人女性。複雑な日本語の二重否定表現に困惑する様子。
「駅まで歩いて行けなくはない」には、日本語話者間の「暗黙の了解」が込められています。「歩けるけれど、遠い」「時間がかかる」「坂が多い」「面倒だ」「雨だからバスが良い」といった様々なニュアンスが含まれるのです。
これは英語の”but”に似た役割ですが、”but”が明示されず、文脈や話し手の意図から読み取る点が日本語の大きな特徴です。英語では具体的な補足が必要です。
- “The station is within walking distance.” (but it’s kinda far.)
- “The station is in walking distance.” (but it will take at least 30 minutes.)
- “The station is in walking distance.” (but it’s uphill the whole way so I wouldn’t do it if I were you.)
- “The station is in walking distance.” (but it’s a pain in the neck to get there.)
- “The station is in walking distance.” (but it is raining, so maybe you should take the bus.)
ネイティブはこれらの「裏の意味」を瞬時に理解できますが、外国人にはこの「言外のニュアンス」を掴むのが極めて困難で、コミュニケーション上の戸惑いを生みます。
「現金しか使えません」と「現金だけしか使えません」の混乱
さらに、「現金しか使えません」といった表現も、外国人学習者にとっては疑問符が付きます。「なぜ素直に『現金だけ使えます』と言わないのか?」という問いは、日本語の独特な思考回路を浮き彫りにします。「現金だけしか使えません」のように「だけ」と「しか」が重なるケースもあり、これは文法的に誤用とされつつも、強調表現として使われることがある、日本語の柔軟性を示す例です。
「私は教師です」と「私が教師です」助詞のニュアンスが伝える違い
アン・クレシーニ氏が指摘するように、助詞「は」と「が」の使い分けも外国人学習者にとって大きな壁となります。例えば、「私は教師です」と「私が教師です」は、どちらも文法的には正しいですが、意味するニュアンスが異なります。「私は教師です」は、単に自分の職業を述べる一般的な情報提示です。一方、「私が教師です」は、「(他の誰でもなく)私が教師だ」という、焦点化や排他的な意味合いを含みます。
この違いは、文脈によって大きく影響され、外国人学習者が正しく使い分けるには多くの経験が必要です。助詞一つで文の意味合いが変化する日本語の特性は、その豊かさの証でもありますが、同時に学習の複雑さを増す要因となっています。
結論: 日本語の奥深さを知る「二重否定」と学習のヒント
日本語の「二重否定」は、単なる文法的な否定を超え、話し手の感情や状況、そして暗黙の了解を伝える重要な表現です。助詞の使い分けも同様に、繊細なニュアンスを伝える日本語の特性を示しています。外国人学習者にとっての「壁」は、日本語の豊かなニュアンスと、言葉の背景にある文化を理解することの重要性を示します。この奥深さを知ることは、異文化理解にも繋がる、興味深い学びと言えるでしょう。日本語学習者は、文法だけでなく、文脈や文化的背景を意識して言葉に触れることで、より深く日本語を理解し、コミュニケーションの幅を広げることができるでしょう。
参考文献
- アン・クレシーニ『世にも奇妙な日本語の謎』(フォレスト出版)
- プレジデントオンライン
- Yahoo!ニュース