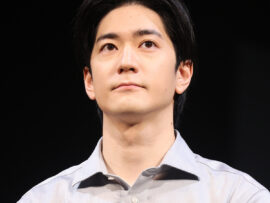近年、「テレビはオワコン(終わったコンテンツ)」とまで言われるようになり、若者を中心にテレビ離れが進んでいます。報道姿勢や取材手法への不信感の高まり、収益低下、さらには話題となったフジテレビのコンプライアンス問題など、様々な負の要素が積み重なり、日本のテレビ業界は大きな転換期を迎えています。このような現状に対し、“テレビの絶頂期”を経験し、15年間にわたりNHKアナウンサーとして勤務した今道琢也氏が、自身の著書『テレビが終わる日』(新潮新書)で深い分析を展開しています。では、なぜテレビへの信頼はこれほどまでに低下し続けているのでしょうか。
 テレビ画面と視聴者のイメージ。日本のメディア、特にテレビに対する信頼性の低下と、それに伴う視聴者離れの問題を象徴しています。
テレビ画面と視聴者のイメージ。日本のメディア、特にテレビに対する信頼性の低下と、それに伴う視聴者離れの問題を象徴しています。
テレビへの信頼が失われた背景:今道琢也氏が指摘する4つの要因
テレビへの信頼がなぜこれほど低下し続けているのかについて、今道氏は多くの人々の意見も踏まえ、その要因を以下の4つの主要な点に大別できると指摘しています。これらの要因は相互に関連し、今日のテレビ不信を形成しています。
- 伝えている内容への不信感: 報道される情報の真実性や公平性に対する疑問。
- 取材姿勢への不信感: ニュースの収集方法や対象へのアプローチに対する疑念。
- 相次ぐ不祥事への不信感: テレビ局自身が関わる一連の問題やスキャンダル。
- テレビという「既得権者」への不信感: 長年にわたり影響力を持つメディアとしての姿勢への批判。
これらの指摘は、メディアが社会に与える影響の大きさと、視聴者が求める透明性との間に生じているギャップを示唆しています。
内容と報道姿勢への深い疑念
特に「伝えている内容への不信感」は、テレビの信頼性を損なう大きな要因の一つです。テレビが伝えるべき情報を正しく伝えているのか、あるいは政治家、芸能人、スポンサーといった「大物」への忖度(そんたく)によって、伝え方が歪められているのではないかという疑念が根強く存在します。
また、他社の不祥事に対しては大きく報道する一方で、自社の不祥事となるとその扱いが小さくなる、というダブルスタンダードに対する不信感も指摘されています。このような都合の良い報道姿勢は、メディアとしての公正性を疑問視させる原因となっています。
さらに、過去にはテレビ番組において「やらせ」や「捏造」といった問題が繰り返し発生してきました。これらの事案は、放送倫理・番組向上機構(BPO)によっても度々取り上げられ、改善勧告がなされてきた経緯があります。やらせや捏造に至らないまでも、物事の誇張表現、一部だけを切り取る一面的な報道、あるいは視聴者の感情を煽るようなセンセーショナルな取り上げ方など、演出上の問題点も視聴者からの指摘が絶えません。これらの積み重ねが、テレビメディア全体への信頼を揺るがしているのです。
まとめ:信頼回復への道筋
今道琢也氏が提示する4つの要因は、日本のテレビ業界が直面する信頼性低下の問題が多角的かつ根深いものであることを示しています。内容の公平性、取材の透明性、そして自浄作用の欠如が、今日のテレビ不信を招いた大きな理由と言えるでしょう。
テレビが社会における重要な情報源としての役割を再確立するためには、これらの不信要因に真摯に向き合い、報道の公正性と倫理基準を徹底することが不可欠です。視聴者が求めるのは、偏りのない正確な情報と、信頼できる報道機関としての姿勢であり、それなくしては「テレビ離れ」の流れを止めることは困難であると考えられます。
参考文献
- 今道琢也 著『テレビが終わる日』(新潮新書)
- Yahoo!ニュース: https://news.yahoo.co.jp/articles/fa1f74c163fffd5ee2083f1740b72a94427a07bc