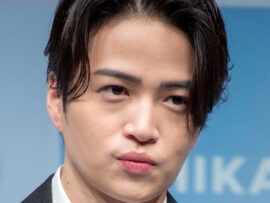2025年7月25日から27日にかけて東京都内で開催された「東京国際合唱コンクール」において、会期中に中国からの参加団体が台湾に対する政治的圧力をかけ、最終日には会場に掲げられた国旗の撤去や、台湾の合唱団が「チャイニーズタイペイ」として紹介されることを余儀なくされる事態が発生しました。これに対し、台湾の外交部(外務省)や台北駐日経済文化代表処は中国側および主催者に抗議を寄せる事態に発展。コンクールを主催する一般社団法人東京国際合唱機構の代表理事である松下耕氏が、訪問先の台北市内で中央社のインタビューに応じ、今回の経緯と胸中に秘めた「歌に国境はない」との強い思いを語りました。
コンクールでの圧力発生と中国側の要求
今回のコンクールには台湾から8団体、中国からは香港を除く5団体が参加していました。特に、中国の3団体は最終日のフォルクロア(民族音楽)部門や、各部門の勝者によるグランプリコンクールに出場する予定でした。
松下氏および同法人の理事である梶山絵美氏によれば、コンクール初日は平穏に終了しましたが、大会2日目の26日になり、中国の参加団体関係者が会場の受付を通じて、台湾の国旗掲示と呼称に関する要求を伝えてきました。調査を進めるうちに、参加団体の一つが中国共産党と強い関係を持ち、他の中国団体に対し「このまま国に帰ったら子どもたちが攻撃されるかもしれない」といった内容を伝え、27日に出場する3団体が連携して要求を行っていたことが判明しました。
しかし松下氏は、中国の団体指揮者が「台湾の旗を降ろさなかったらボイコットする」と告げながらも、その表情には無念さが滲み出ており、彼らの本意ではないという色が見えたと明かしました。
台湾側からの抗議と主催者の苦渋の決断
今回の事態に対し、台北駐日経済文化代表処からも主催者への抗議が寄せられました。問題解決の糸口が見つからず、26日夜には一時、中国側が翌日の参加を取りやめるという状況にまで至りました。しかし、松下氏は「子どもたちに罪はない」「歌に国境はないはず」という強い信念から、かねてより親交の深い台湾の合唱団に対し、苦渋の決断への理解を求め、承諾を得ることができました。松下氏はこれまで合唱の仕事で数十回も台湾を訪れており、一方で中国の合唱団とは約20年間、一緒に仕事をしていないと付け加えています。この背景には、長年にわたる台湾との深い交流と信頼関係がありました。
最終日の対応と「歌に国境を作ることの方が敗北」
結果として、27日の最終日には、台湾や中国を含め、全ての参加国の国旗が会場から撤去されました。台湾の合唱団が入場する際には、正式呼称として「チャイニーズタイペイ」が用いられましたが、司会者が紹介する際には、何らかの形で「台湾」という言葉が織り込まれる対応が取られました。
この対応について松下氏は「全く納得がいっていない」と正直な心境を吐露しました。しかし、「歌に国境を作ることの方が敗北だと思った」と語り、最終的に予定していた全ての合唱団がステージに上がり、互いに拍手を送り合えたことこそが重要であったと振り返りました。この決断は、政治的な圧力に屈することなく、音楽の持つ普遍的な力と子どもたちの夢を最優先するという主催者側の強い意志を示すものでした。
 東京国際合唱コンクール会場の様子。中国からの圧力で台湾の国旗が撤去された後の大会2日目の光景。
東京国際合唱コンクール会場の様子。中国からの圧力で台湾の国旗が撤去された後の大会2日目の光景。
主催者の揺るぎない理念:「国境を越え 私達は一つ 平和の歌よ 晴海に響け」
インタビューの最後に、松下氏らは参加者が練習会場と本番会場を行き来する際に利用した貸し切りバスの写真を提示しました。そのバスには「国境を越え 私達は一つ 平和の歌よ 晴海に響け」(晴海は会場である第一生命ホールがある地名)というメッセージが書かれていました。松下氏は、このメッセージこそが「主催者の偽らざる理念です」と話し、今回の困難な状況下においても、音楽を通じて平和と一体感を追求するというコンクール本来の目的が変わらないことを強調しました。
結論
今回の東京国際合唱コンクールで発生した一連の出来事は、国際的な文化交流の場においても政治的な圧力が及ぶ現実を浮き彫りにしました。しかし、主催者である松下耕氏の「歌に国境はない」「子どもたちに罪はない」という信念に基づいた苦渋の決断は、音楽の力を通じていかなる障壁も乗り越えようとする強いメッセージを世界に発信しました。文化イベントが政治的緊張の舞台となる中でも、純粋な音楽への情熱と平和への願いを優先するその姿勢は、多くの人々に感銘を与えています。