漫画界の巨匠、水木しげる氏(1922〜2015年)が2025年7月に「コミック界のアカデミー賞」と称されるアイズナー賞の殿堂入りを果たすことは、日本の漫画史における画期的な出来事です。この栄誉の背景には、水木氏が2012年に同賞最優秀アジア作品賞を受賞した『総員玉砕せよ!』への国際的な高い評価があります。この傑作において、兵士たちに自決や玉砕を迫る「木戸参謀」という人物が登場しますが、実はこのキャラクターには実在のモデルがいました。その人物とは、戦後に発行された日記や回想録によって、忠誠心と責任感に溢れる元軍人として知られていた松浦義教氏です。なぜ水木氏は、このように世間から立派とされた人物を告発するような作品を、あえて描いたのでしょうか。この問いへの答えは、林英一氏の新刊『南方抑留 日本軍兵士、もう一つの悲劇』(新潮選書)によって、その背景が明らかにされています。
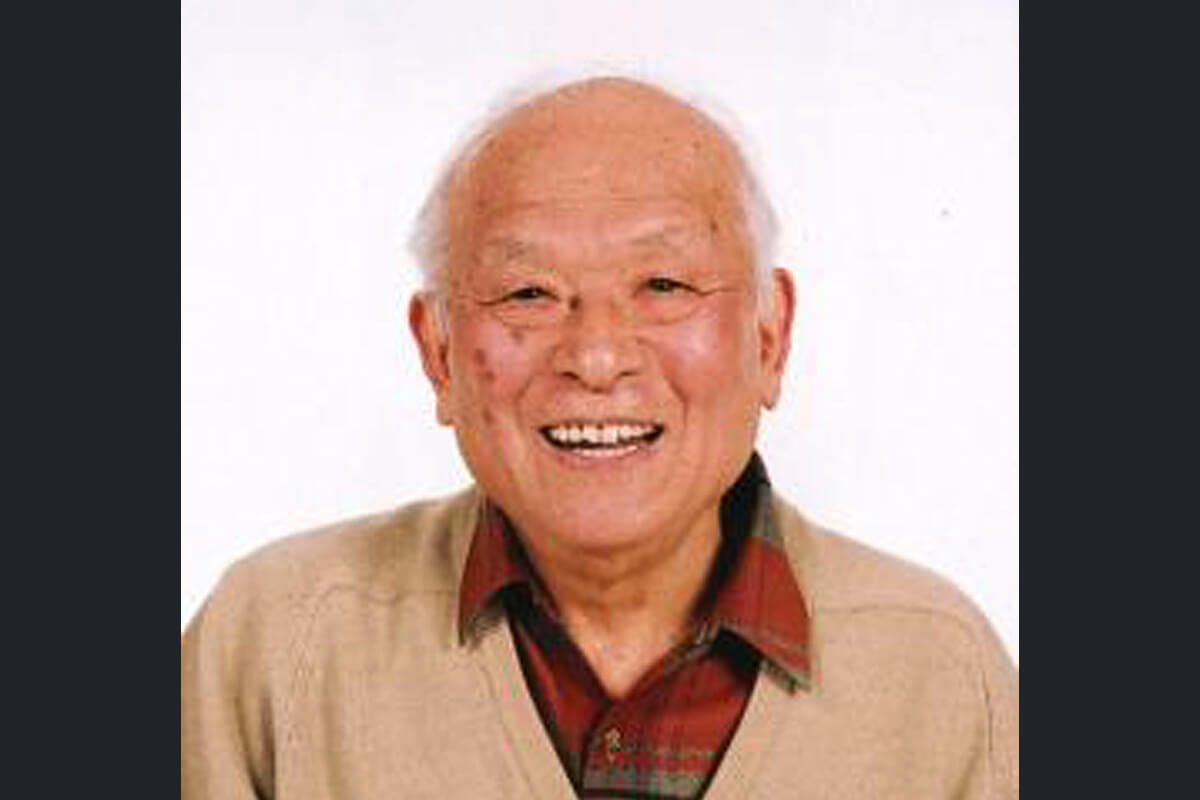 漫画家・水木しげる氏、アイズナー賞殿堂入りを果たす
漫画家・水木しげる氏、アイズナー賞殿堂入りを果たす
エリート参謀・松浦義教の知られざる側面
松浦義教は1908年、山口県萩市に生まれ、熊本陸軍幼年学校、陸軍士官学校(四二期)を卒業した、将来を嘱望されたエリート軍人でした。しかし、二・二六事件への連座疑惑で陸軍刑務所に収監されるという挫折も経験しています。釈放後は上司の計らいで満洲とソ連の国境守備隊や牡丹江の第三軍参謀部で勤務し、1943年には第三八師団参謀として激戦地ラバウルに派遣されました。
終戦後、松浦は日本への復員を目前にしながらも、今村大将の要望を受け、戦犯裁判の弁護将校・弁護人としてラバウルに留まることを決意します。この期間の日記について、彼は連合軍の検閲を避けるため、一般的な内容は拙いながらも英文で記し、秘匿すべき戦犯事項は記号や隠語を多用した日本文で細字で挿入したと説明しています。この偽装された日記の原本は、帰国時に秘密裏に持ち帰った「遺書」として扱われ、戦後の彼の人生を大きく左右しました。
帰国後、松浦は1949年に光文社からの出版を試みましたが、GHQの検閲に阻まれ陽の目を見ませんでした。その後、7度にわたる改稿を重ね、彼が90歳で大往生を遂げる前年の1998年に、ようやく『真相を訴える──ラバウル戦犯弁護人の日記』として2000部が自費出版されました。この出版までの長い道のりは、松浦がいかに自らの体験と日本軍の実態を後世に伝えようとしたかを示しています。
 第二次世界大戦中、ラバウルに配備された日本軍の航空部隊
第二次世界大戦中、ラバウルに配備された日本軍の航空部隊
水木しげる作品と歴史の重層性
水木しげる氏が『総員玉砕せよ!』で松浦義教をモデルとした人物を厳しく描いたのは、単なる告発ではなく、戦争という極限状況下における人間の本質や軍隊組織の闇を深く掘り下げようとした結果と言えるでしょう。松浦氏が戦後に記した「たとえ戦さは敗れても、将官が帰りたがってはならない」といった模範的な言葉と、作品内で描かれる兵士に自決を迫る参謀の姿との間には、大きな隔たりがあります。
水木氏は、表面的な「立派な軍人」のイメージだけでなく、その裏に隠された陰惨な史実、特に玉砕命令という非人間的な行為を追求することで、戦争の真の悲劇と、それに加担した者たちの複雑な心理を描き出しました。この作品は、日本軍が南方で経験した悲劇の一端を浮き彫りにし、戦史の語られ方、そして歴史の真実を多角的に問い直す契機となっています。水木氏の殿堂入りは、単に漫画家としての功績だけでなく、戦争の記憶と向き合い、その真実を追求し続けた彼の姿勢が国際的に評価された証と言えるでしょう。
参考文献
- 林英一著『南方抑留 日本軍兵士、もう一つの悲劇』(新潮選書)
- 松浦義教著『真相を訴える──ラバウル戦犯弁護人の日記』(自費出版)






