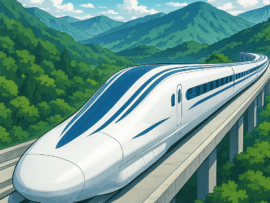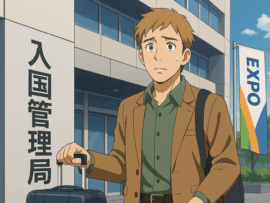NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』において、若年寄・田沼意知(宮沢氷魚)が江戸城中で将軍の警護役である佐野政言(矢本悠馬)に斬られ命を落とす衝撃的な場面が描かれました。佐野は切腹したものの、その直後から世間の反応は奇妙な様相を呈します。被害者である意知の葬列には石が投げられ、一方で佐野は「佐野福の神様」「佐野世直し大明神」とまで呼ばれ、人々から崇められる存在へと「仕立て上げられて」いくのです。この歴史的事件の裏には、現代にも通じる巧妙な世論操作のメカニズムが隠されていました。
「佐野大明神」に祭り上げられた背景:庶民の不満と情報操作
佐野政言が斬った田沼意知が「悪」であり、佐野が「善」であるかのように世間が認識し始めたのは、井戸端の女たちの噂から始まりました。「佐野様が田沼の息子を切ったから、米の値が下ったんだろ?」といった根拠のない話がまことしやかに語られ、ついには佐野を神格化する動きへと発展していきます。蔦屋重三郎(横浜流星)が「斬られたほうが石投げられて、斬ったほうが拝まれるってなあ、さすがについていけねえです」と語る通り、この状況は当時の常識では理解しがたいものでした。
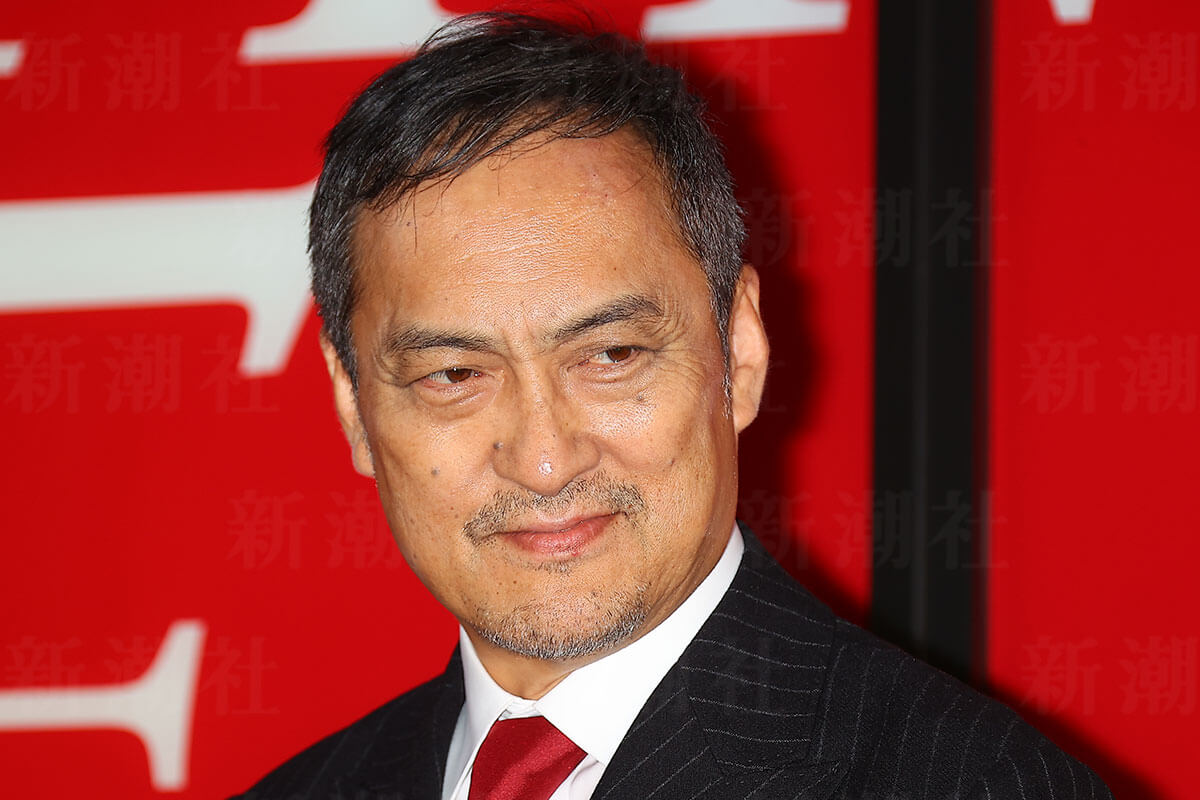
そして、佐野の菩提寺に「佐野世直し大明神」の幟が立てられたのを見た蔦重は、この現象が意図的に「仕立て上げられている」と気づきます。特定の情報が流され、世論が撹乱され、ある方向に誘導される。この「仕立て上げ」は、まさに現代社会で頻繁に目にする情報操作やフェイクニュースによる世論誘導と驚くほど重なる現象です。
田沼政権下の米価高騰と「佐野の手柄」にされた真相
佐野意知が暗殺された天明4年(1784年)3月当時、江戸の庶民は極度の疲弊状態にありました。その主な原因は、天明の大飢饉の真っただ中にあったことと、それに伴う深刻な米価高騰です。飢餓に苦しむ農民たちが米の買い占めを行う商人宅を打ち壊す事件も発生しており、米価高騰はそのまま田沼意次(渡辺謙)と意知父子の政治に対する不満へと直結していました。
しかし、田沼政権が無策だったわけではありません。この困難な状況下で、田沼意次らは大阪商人の買い占め米6万5000石を徴収し、江戸へ廻送させるという施策を実行していました。この政策は功を奏し、米価は下落に向かいます。ところが、よりによって米価が下がり始めたのは、佐野が切腹した翌日のことでした。この偶然が「べらぼう」で描かれたように、「米価の下落は佐野様のおかげ」という誤解を生み、佐野が「世直し大明神」として祀られるに至ったのです。実際に佐野が葬られた徳本寺(台東区西浅草)には、連日多くの参詣者が押し寄せ、墓所に供える花や線香、さらには墓にかける水を売る店まで並ぶほどだったといいます。
田沼意知暗殺の裏側に隠された政治的意図
佐野政言による田沼意知暗殺事件は、佐野の一存で行われたとは考えにくいというのが歴史家の一致した見解です。『べらぼう』では、次期将軍の父である一橋治済(生田斗真)が裏で糸を引いていたかのように描かれていますが、これは史実にも通じる見方です。
当時のオランダ商館長イサーク・ティチングは、この事件について「この殺人事件に伴ういろいろの事情から推測するに、もっとも幕府の高い位にある高官数名が事件にあずかっており、また、この事件を使嗾(そそのかすこと)しているように思われる」と記録に残しています。この記述は、意知暗殺事件が単なる個人的な怨恨によるものではなく、田沼意次の改革路線に反対する勢力による政治的な企て、すなわち世論を動かすための陰謀であった可能性を強く示唆しています。佐野政言は、その陰謀の道具として利用された側面があったのかもしれません。
結論:歴史が語る世論操作の教訓
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』で描かれた佐野政言が「世直し大明神」に祭り上げられた現象は、当時の庶民が抱えていた社会への不満と、その不満を特定の方向に誘導しようとする巧妙な情報操作が結びついた結果でした。米価下落という偶然が、情報操作の絶好の機会となり、佐野を英雄視する世論が形成されていったのです。
この江戸時代の出来事は、現代社会においても、フェイクニュースや偏った情報が瞬く間に拡散し、世論が特定の意図によって操作され得る危険性を示唆しています。私たちは歴史から学び、表面的な情報に惑わされることなく、多角的な視点から物事を捉え、情報の真偽を冷静に見極めるリテラシーを養うことの重要性を再認識すべきでしょう。
参考文献