東京の交通網の要である山手線には、その駅名にまつわる興味深い「なぜ?」が存在します。中でも「品川駅」が「品川区」ではなく「港区」に位置しているという事実は、多くの人々にとって不思議に感じられるかもしれません。この一見矛盾した状況は、鉄道の歴史、そして東京という都市が経験してきた大規模な行政区画の再編が複雑に絡み合った結果生まれたものです。本稿では、『山手線「駅名」の謎』(鉄人社)の記述を基に、品川駅の所在地にまつわる歴史的経緯と、その背景にある行政の変遷を深く掘り下げていきます。
鉄道事業法から見る駅名規定の柔軟性
鉄道駅の設置や新設に関しては、1986年(昭和61年)に交付された鉄道事業法や、翌年に施行された同法施行規則によって「認可」が義務付けられています。しかし、この認可は主に安全性や事業運営の円滑性を目的としたものであり、実は駅名に関する具体的な法的制限は特段設けられていません。
例えば、鉄道事業法第4条第1項第6号や同施行規則第5条第5号、あるいは法第9条第1項と同施行規則第27条第2号イなどを参照しても、駅名自体の法的拘束力は非常に緩やかであることがわかります。現代の法律でさえこのような柔軟性があるのですから、明治時代から大正時代にかけて開業した山手線の駅名に至っては、比較的自由な発想で命名されたケースが少なくありません。品川駅の命名もまた、当時の自由な慣習の中で行われたものと言えるでしょう。
「品川駅」誕生物語:宿場町から離れた立地の背景
品川駅の名称は、かつて東海道五十三次の最初の宿場町であった「品川宿」に由来しています。しかし、1872年(明治5年)に開業した初代品川駅は、この品川宿の中心地から約1kmも離れた場所に建設されました。これはなぜでしょうか。
旅行・鉄道関連の著書を多数執筆している内田宗治氏の推測によれば、品川宿は当時、旅館や商家、民家が密集しており、鉄道の線路や駅を建設するためには広範な土地の立ち退き問題が発生し、複雑な交渉や長期間を要することが避けられなかったためです。そこで、よりスムーズに建設を進めるため、当時比較的土地が確保しやすかった現在の港区高輪付近に初代駅が設けられました。
1878年(明治11年)に東京が15区に分割された際、品川駅は「芝区」の南端に組み入れられます。一方で、駅名の由来となった品川宿の地は、東京市の外に位置する「荏原郡」に属することになりました。これにより、駅とその名前の由来が行政的に異なる区域に分かれるという状況が生まれました。
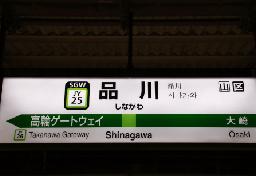
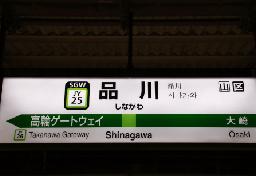 東海道の宿場町「品川宿」に由来する品川駅の遠景
東海道の宿場町「品川宿」に由来する品川駅の遠景
東京の行政区画再編と品川駅の変遷
品川駅はその後、1896年(明治29年)に現在の品川駅の位置へと移転しました。しかし、駅の場所が変わっても、東京の行政区画の再編は止まりませんでした。

 1896年(明治29年)頃の品川駅と、当時すぐそばまで迫っていた海辺の風景
1896年(明治29年)頃の品川駅と、当時すぐそばまで迫っていた海辺の風景
1932年(昭和7年)には、東京市が周辺の町村を編入し、市域を大幅に拡張してそれまでの15区から35区体制へと移行しました。この時点でも品川駅は現在の港区に当たる区域に位置しており、行政区画の拡大と共にその所属も変遷していきました。
そして、品川駅が「港区」に編入される決定的な出来事が起こります。第二次世界大戦後の1947年(昭和22年)、戦災によって東京の人口は大きく減少し、各区の人口バランスが大きく崩れました。この不均衡を是正し、行政効率を高める目的で、東京は従来の35区から現在の23区へと大規模な再編が行われました。この区画整理の際、品川駅は隣接する「品川区」があったにもかかわらず、その当時駅が位置していた区域が「港区」の一部として再編されたため、結果的に港区に編入されることになったのです。
このように、品川駅が港区に存在するという状況は、駅が建設された当初の用地事情、その後の行政区画の変遷、そして特に戦後の大規模な都市再編という、複数の歴史的要因が複雑に絡み合って形成されたものと言えます。これは、行政の効率化を図る中で生じた、ある種の「ちぐはぐさ」を象徴する出来事でもあります。
目黒駅も同様のケース:山手線に潜む区画の謎
山手線には、品川駅と同様に駅名と所在地が異なる駅が存在します。その一つが「目黒駅」です。目黒駅は「目黒区」ではなく、実は「品川区」に位置しています。これもまた、過去の行政区画の再編や駅の建設事情が関係しており、山手線沿線にはこうした興味深い「駅名の謎」が他にも隠されていることを示唆しています。
結論
品川駅が「港区」に位置するという一見すると不可解な事実は、単なる誤解や偶然ではありません。これは、明治時代の鉄道建設における用地確保の課題に始まり、東京市が経験した複数回の大規模な行政区画再編、特に第二次世界大戦後の23区再編という歴史的経緯が深く関わっています。鉄道駅の設置基準の柔軟性と、時代ごとの都市計画の優先順位が交錯する中で、現在の「品川駅(港区)」という特異な状況が生まれたのです。
このような駅名と所在地のズレは、東京という都市が常に変化し、その姿を調整してきた証でもあります。日常的に利用する山手線の駅一つにも、知られざる歴史の深さと都市の変遷が隠されていることを改めて感じさせられます。
参考文献
- 小林明 (著), 『山手線「駅名」の謎』, 鉄人社, 2025年.
- 鉄道事業法 (昭和六十一年法律第九十二号)
- 鉄道事業法施行規則 (昭和六十二年運輸省令第四十一号)






