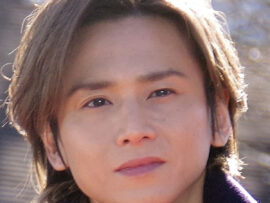「ウーバーで注文しようとしたら、配達エリア外だった」。先日、地方に住む友人からこんな話を聞きました。彼の住む人口約10万人の街では、ファストフード店や郊外型大型ショッピングセンターがあるにもかかわらず、ウーバーイーツや出前館で注文できる飲食店はごく一部に限られているのが現状です。筆者自身も東京と香川県丸亀市での二拠点生活を送っており、丸亀市郊外の自宅(駅から約4キロメートルと、決して田舎ではない場所です)では、フードデリバリーが利用できないケースが頻繁にあります。都市部では当たり前のように利用できるフードデリバリーですが、車の利用が面倒な地方でこそ、その利便性を強く感じることが少なくありません。新型コロナウイルス感染症のパンデミック期に急成長を遂げ、社会インフラの一部となったフードデリバリー業界は、現在、その構造的な矛盾と限界に直面し、大きな岐路に立たされています。本稿では、このフードデリバリー業界が抱える根本的な問題点について深く掘り下げていきます。
 日本の地方におけるフードデリバリーの課題と現状を象徴する配達員のイメージ
日本の地方におけるフードデリバリーの課題と現状を象徴する配達員のイメージ
地方と都市部で顕著なサービス格差
前述の通り、地方都市ではフードデリバリーの利用に大きな制約があります。筆者が生活する丸亀市でも、都心部と比べて選択肢が圧倒的に少なく、自宅が「配達エリア外」となることが日常茶飯事です。これは、単に利用者の不便さにとどまらず、地方におけるフードデリバリーサービスの普及と定着を妨げる根本的な要因となっています。都市部では競合するプラットフォームがひしめき合い、多種多様な飲食店が利用できますが、地方では需要の規模や配達効率の問題から、サービス提供が限られがちです。このサービス格差は、パンデミックを機に拡大したデリバリー需要の受け皿となりきれていない地方の現状を如実に示しています。
出前館の苦境が示す業界の課題
フードデリバリー業界全体の限界と課題は、出前館の最新決算からも明らかです。2025年8月期第3四半期(2024年9月~2025年5月)の連結売上高は301億円と、前年同期比で約21%の大幅減を記録しました。営業損失は約31億円に縮小したものの、依然として赤字が続いています。さらに、2025年8月期の通期決算予想では、当初の100万円の黒字見込みから一転、48億円の赤字へと大幅な下方修正となりました。決算説明資料によれば、出前館のアクティブユーザー数は2022年以降減少し続けており、売上高の低迷と相まって、事業立て直しが喫緊の課題となっています。このような業績悪化の背景には、競合であるウーバーイーツの圧倒的な存在感が強く影響していると考えられます。
 配達員の厳しい現実と、都市部と地方におけるフードデリバリーサービスの違いを示す風景
配達員の厳しい現実と、都市部と地方におけるフードデリバリーサービスの違いを示す風景
「ウーバーの一人勝ち」構造と業界全体の停滞
日本のフードデリバリー市場において、自転車やバイクによる配送モデルを本格的に普及させたのはウーバーイーツの上陸がきっかけでした。1999年からサービスを提供していた出前館も、ウーバーイーツの登場以前は存在感が薄かったと言わざるを得ません。「Uber」のロゴが入った大きなバッグを背負って街中を駆け巡る配達員の姿は、一般の人々に「フードデリバリーといえばウーバー」という強いイメージを植え付けました。この「先行者利益」を享受したウーバーイーツが唯一、二桁成長を達成し、業界トップの座を不動のものにしています。実際、同業であるウォルトも今期の決算は赤字であり、ウーバーイーツの一人勝ち状態が業界全体の停滞感を招いています。この状況は、新規参入の困難さや、持続可能なビジネスモデル構築の課題を浮き彫りにしています。
業界の持続可能な発展への展望
現在のフードデリバリー業界は、都市部と地方におけるサービス格差、一部企業の深刻な赤字、そして「一人勝ち」構造による市場の停滞という多岐にわたる課題に直面しています。パンデミック期の特需が収束した今、企業は収益性向上と同時に、地方を含むより広範なニーズに応えるための新たな戦略を模索する必要があります。過度な割引競争から脱却し、配達員の労働環境改善、効率的な配送網の構築、そして地域に根ざしたサービス提供モデルの確立が、業界が持続的に発展していくための鍵となるでしょう。
参考文献
- Yahoo!ニュース: 「頼みたいときに頼めない……地方のフードデリバリー事情」
https://news.yahoo.co.jp/articles/77442e79b45d0b2e9e9c04772e7f4a4aa358cdca