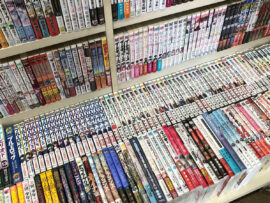今年1月、埼玉県八潮市の県道交差点で発生した道路陥没事故は、大型トラックが飲み込まれ、運転手が死亡するという衝撃的なものでした。日々の生活で当たり前のように利用している道路が、突如として危険な「地獄の入口」と化す可能性があるという事実に、多くの人々が強い不安を感じたことでしょう。この事故の原因は、1983年に敷設された水道管の老朽化による破損で、土砂が管内に流入し、地下に空洞が形成されたこととされています。この事実は、目に見えない地下で同様の現象が日本各地で進行している可能性を示唆しており、その潜在的な危険性に目を向けざるを得ません。
読売新聞が示す全国の現状:見えない地下の危険
私たちの日々の不安を裏付けるかのように、7月27日の読売新聞朝刊に、道路陥没に関する詳細な記事が掲載されました。同紙のデータ分析によると、2015年度から2024年度までの10年間に全国の国道で確認された陥没や空洞は、合計1100件以上に上ります。注目すべきは、そのうちの4割強にあたる509件(44%)が、八潮市の事故と同様に、埋設管などの破損による土砂の「吸い込み」を原因としていた点です。この「吸い込み」は、主に埋設管の腐食や接合部の劣化といった老朽化に起因するとされています。その他の原因としては、施工不良が259件(22%)と多く報告されています。
国道以外の道路にも広がるリスク
読売新聞が分析対象としたのは「国道」のみであり、八潮市で陥没が発生した「県道」は含まれていません。もし、都道府県道や市町村道といった下位の道路も含めれば、道路陥没や地下空洞が確認された箇所の総数は、1100件をはるかに超えることは確実です。これは、日本全体の道路インフラが抱える広範な問題を浮き彫りにしています。
 埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故現場の様子。大型トラックが陥没穴に落ち込んでいる。
埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故現場の様子。大型トラックが陥没穴に落ち込んでいる。
進行する下水道管の老朽化:寿命と現実のギャップ
日本の下水道管の総延長は約49万キロメートルに及び、その「寿命の目安」とされる50年を経過した管の割合は、2023年時点ですでに全体の8%に達しています。この割合は、2030年には16%にまで増加すると予測されており、老朽化が急速に進行している現状がうかがえます。さらに、八潮市で事故を引き起こした水道管は、埋設後わずか40年余りしか経過していなかったことを考えると、「50年を経過していないから安全」とは決して言い切れません。埋設された環境や管の種類によっては、より早期に劣化が進む可能性もあるのです。
日本に住み、日本の道路を使い続ける以上、八潮市のような悲劇的な事故が二度と起きないことを願うばかりですが、果たしてこうした道路陥没や地下空洞化を完全に防ぐことはできるのでしょうか。抜本的な対策と持続的なインフラ維持管理が、喫緊の課題として求められています。
参考文献: