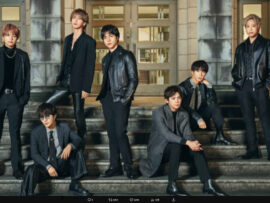少年法の根底に流れる理念は、罪を犯した少年を社会で「更生」させることにあります。しかし、この「更生」という言葉自体、法的な明確な定義を持たないのが実情です。長年にわたり少年事件の取材を続けてきたジャーナリストの川名壮志氏は、その曖昧さに疑問を投げかけます。彼が新聞記者として初めて少年事件に深く関わったのは2004年の佐世保小6女児同級生殺害事件でした。被害者の父親が自身の直属の上司であったという衝撃的な経験は、彼の取材姿勢に大きな影響を与え、加害者側の内面にも深く迫るきっかけとなります。本稿では、川名氏の著書『酒鬼薔薇聖斗は更生したのか 不確かな境界』から、少年法における「更生」の真の意味、そして社会が少年犯罪にどう向き合ってきたかを多角的に考察します。
神戸連続児童殺傷事件が問いかける「更生」の現実
1997年に発生した神戸連続児童殺傷事件は、当時14歳だった「酒鬼薔薇聖斗」を名乗る少年による残忍な犯行として、日本社会に深い衝撃を与えました。現在、彼は一般社会で生活しているとされますが、果たして彼は「更生」したと言えるのでしょうか。再犯を起こしていなければ更生したと見なされるのが法的な一つの側面である一方で、多くの人々の中には拭い去れない釈然としない思いが残ります。川名氏は、この感覚こそが「更生」という概念の複雑さと、社会が抱える「少年」像の変遷を浮き彫りにしていると指摘します。罪を悔い改める「更正」とは異なり、社会の中で再び生きる力を育む「更生」は、単純な問いでは答えが出ない領域にあるのです。
 川名壮志氏による新潮新書『酒鬼薔薇聖斗は更生したのか 不確かな境界』の書影。少年法における「更生」の複雑な問いを投げかける作品。
川名壮志氏による新潮新書『酒鬼薔薇聖斗は更生したのか 不確かな境界』の書影。少年法における「更生」の複雑な問いを投げかける作品。
時代と共に変化する「少年」の認識と報道
戦後、少年法が施行されて以来、20歳未満の加害者の実名報道は原則として禁じられてきました。しかし、実際には報道の自由が優先され、匿名報道のあり方は時代によって大きく変化しています。例えば、1960年の浅沼稲次郎刺殺事件では、17歳の山口二矢が実名だけでなく顔写真も報じられました。また、1968年に連続ピストル射殺事件を起こした永山則夫は、手記『無知の涙』を出版し、少年事件への社会の注目を集めるきっかけとなりました。
しかし、1970年代以降は少年事件の匿名報道が定着し、社会の焦点は校内暴力や家庭内暴力、そして「いじめ」問題へと移っていきました。特に神戸連続児童殺傷事件以降、少年事件においては「精神鑑定」がトレンドとなりました。本来、精神鑑定は刑事責任能力を判断するために行われますが、少年事件では事件の動機や背景を解明する目的で用いられることが多くなりました。これは個人の特性に光を当てるという意味では有意義であるものの、川名氏は、多くの場合、家庭環境や教育の歪みなど社会的な要因が深く関わっているにもかかわらず、その点が十分に考慮されず、安易に個人の問題として片付けられている傾向があると指摘します。その結果、少年犯罪は社会全体が共有すべき問題ではなくなり、2010年代以降、少年事件の報道自体が減少している現状があり、これは世論の反映とも言えるでしょう。
法律が示す「少年」の多様な位置づけ
「少年」という存在の捉え方は、法律によっても一貫していません。民法改正によって成年年齢が18歳に引き下げられたことは記憶に新しいですが、少年法においては20歳未満が「少年」とされ、特に18歳と19歳の「特定少年」の位置づけは、それぞれの法律によってちぐはぐな扱いを受けています。
川名氏は、このように時代という縦軸で見ても、社会が「少年」に向ける視線は変化し続けており、法律という横軸で見ても、その捉え方がバラバラである点を強調します。つまり、「少年」という存在そのものが、非常に不確かで流動的な現実を抱えているのです。
結論:不確かな「更生」と社会の責任
少年法の理念である「更生」は、一見すると明確な目標のように見えますが、その実態は非常に複雑で、明確な答えを導き出すことは困難です。川名氏自身も、この問いに対するモヤモヤした感情を抱え続けています。
しかし、どのような事件であっても、その当事者だけの問題ではなく、社会全体が負うべき責任が必ず存在します。この事実から目を背けず、常に問い続け、深く考え続けることこそが、真の意味での「更生」を社会全体で支えるために不可欠であると、川名氏は強く訴えかけています。少年犯罪を通じて、私たち一人ひとりが社会のあり方、そして「更生」という概念を問い直すことが求められているのです。
参考文献
- 『酒鬼薔薇聖斗は更生したのか 不確かな境界』(川名壮志 著)新潮新書
- 「週刊文春」編集部/週刊文春 2025年7月31日号
- Yahoo!ニュース(出典記事)