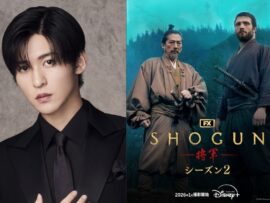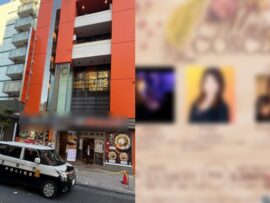近年、誰もがその名を知る大手企業が数千人規模の希望退職を募集するニュースが相次ぎ、世間の注目を集めています。パナソニックや日産など、かつて終身雇用の象徴とされた企業でさえ、大規模な「平時のリストラ」が常態化しつつある現状は、多くのビジネスパーソンにとって自身のキャリアを深く考えるきっかけとなっています。このような状況下で、会社からの希望退職勧奨を受けた際、「さっさと辞める人」と「それでも会社にしがみつこうとする人」の間に決定的な違いがあることが浮き彫りになります。この差は一体どこにあるのでしょうか。
大手企業の「平時リストラ」が常態化
日本の大企業において、近年、数千人単位の希望退職募集が当たり前のように行われるようになりました。これは、経済状況の悪化や経営不振が直接的な原因ではない「平時のリストラ」として認識されており、企業の事業構造転換や成長戦略の一環として実施されるケースが目立ちます。このような環境下で、特に氷河期世代やミドル世代の従業員は、自身のキャリアの岐路に立たされることになります。彼らが希望退職勧奨に直面した時、すんなりと次の道へ進む者と、何としてでも会社に留まろうとする者との間で、その行動基準と背景には明確な違いが存在します。
 大手企業での希望退職を検討するビジネスパーソンのイメージ
大手企業での希望退職を検討するビジネスパーソンのイメージ
「さっさと辞める人」と「会社に残る人」を分ける決定的な要素
希望退職募集に「さっさと乗る人」と「会社に残ろうとする人」の決定的な違いは、「ポータブルスキル」の有無にあります。ポータブルスキルとは、特定の企業や業界に限定されず、様々な環境で通用する汎用性の高いスキルのことです。前回の連載でも詳しく解説しましたが、専門職種のプロフェッショナリティ、語学力、マネジメント力などがこれに該当します。
日本の雇用システムの性質上、ミドル世代の多くは、企業内でしか通用しない「企業内特殊スキル」に特化してキャリアを積んできた傾向があります。彼らはその会社での「生き方」には長けていても、社外での市場価値や汎用的な技能を身につけているケースは少ないのが現状です。
大規模な希望退職募集があった際、「さっさと辞める人」は、自身のキャリアを主体的に形成し、社外での人脈を築き、市場で通用するポータブルスキルを身につけている人たちです。彼らは会社に過度に依存しておらず、退職金の上乗せといった好条件が提示されれば、「それなら辞めます」と即決できる判断力と準備があります。
一方、「会社に残る人」は、職務経歴書に書けるようなポータブルスキルに乏しい場合が多いです。職務経歴書はポータブルスキルを記述する場であるため、それがなければ自身の市場価値をアピールすることが困難になります。このような状況に直面すると、彼らは「崖っぷちに立たされても飛べない」状態に陥り、会社に留まることしか選択肢がないと感じてしまうのです。
終わりに
大手企業における希望退職の常態化は、もはや他人事ではありません。この潮流の中で、自らのキャリアを主体的に選択し、変化に対応していくためには、いかにポータブルスキルを磨き、社外でも通用する人材となるかが極めて重要です。企業内での経験だけでなく、普遍的なスキルを意識的に習得していくことが、将来の不確実性に対する最大の備えとなるでしょう。
参考文献:
- 安藤 健, 奥田由意. 人材研究所ディレクター.